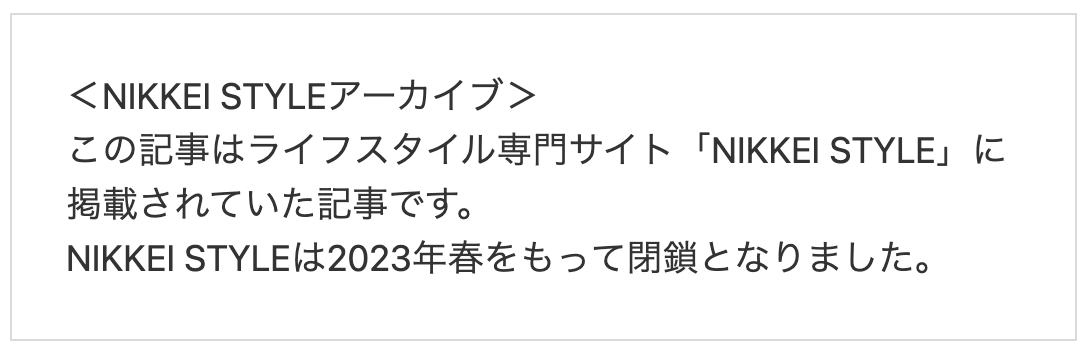M・スコセッシ監督が語る 『沈黙』を映画化した意味

マーティン・スコセッシ監督の最新作となる『沈黙-サイレンス-』が1月21日から日本公開となる。遠藤周作の原作と出合ってから28年、いくつもの困難を乗り越えて映画化を実現したという、まさにスコセッシ監督のライフワークともいうべき作品だ。
世界の映画人から尊敬され、アカデミー賞監督賞(『ディパーテッド』)にも輝く世界的な巨匠が、それほどまでにほれこんだ原作とは、どのような話なのか。
舞台は17世紀、江戸初期の長崎。幕府による激しいキリシタン弾圧下で、捕らえられて棄教したとされる宣教師フェレイラの消息をたどるべく、弟子の若きポルトガル人司祭2人が危険を冒して日本に潜入する。そこで目にしたのは、隠れキリシタンに対する想像を絶する仕打ちや拷問だった。司祭の1人ロドリゴは、これほど多くの殉教者の血が流れているのに、それをただ見つめているだけの神の存在に、次第に疑問を抱くようになる。そして、長崎奉行の井上筑後守が語りかける「棄教すれば、信者を助けられる」という言葉に、固い信仰心が揺らいでいく…。
タイトルの「沈黙」とは、神の無言のことである。
「宣教師も暴力を持ち込んだ」

映画公開を前に、スコセッシ監督が来日。記者会見で、この映画で描いた隠れキリシタンへの弾圧について、こう語った。
「隠れキリシタンへの拷問は暴力でしたが、西洋からやってきた宣教師も同じように暴力を持ち込んだのではないでしょうか。『これが普遍的な唯一の真実である』とキリスト教を持ち込んだわけです。それに対処するには、彼らの傲慢をひとつずつ崩していくしかないと、日本の為政者は考えたのです。そこでリーダーである宣教師にプレッシャーを与え、上から崩していく方法を見いだしました。映画の中でも、ロドリゴの傲慢が崩されていき、慈悲心を身をもって知ることで、真のキリシタンになっていきます。要するに、権威的なアプローチで教えを説くのではなく、キリスト教の中の女性的な面をもって説くのが、日本で受け入れられるやり方ではなかったでしょうか。隠れキリシタンの人たちも、実はキリスト教のそういう面にひかれていたのではないかと思うのです」
スコセッシ監督が遠藤周作の原作小説を知ったのは1988年。イエス・キリストを悩める人間として描いて物議をかもした『最後の誘惑』を撮った後、聖職者向けの上映会の際に大司教から本をプレゼントされたという。読んだ監督は、大きな衝撃を受ける。
「熱烈なカトリックの家庭で育ったため、私と宗教とのかかわりはとても深いものでした。ローマカトリック教の精神性はいまだに私の基盤となっています。この年になっても、信仰や疑い、弱さや人間のありようについて考え、疑問を感じていますが、それらは遠藤さんが『沈黙』で描いていたテーマでした」(プロダクションノートから)
遠藤周作が問いかけた「母なる神」

遠藤周作は、小学生のころ両親が離婚して、伯母の影響で洗礼を受け、カトリック教徒となる。慶応大学卒業後はフランス留学もするが、西欧的なキリスト教のあり方にはずっと疑問を抱いてきたという。
神について語ったエッセー『私にとって神とは』では、「(著作の『イエスの生涯』に対して)浄土真宗的なものにイエスを歪曲しているという批評があるが、どう思うか」という質問に対して、「否定しません。私の考える日本的宗教意識-それを私は西欧の父性的宗教意識と違う母性的宗教意識だと思っていますが-で捉えたイエス像だからです」と答えている。
日本で一般的に考えられているキリスト教のイメージは、「厳しく罰する、父なる神」だろう。それに対して「優しく包み込む、母なる神」の働きかけはあるのだろうか。そう問いかけたのが、原作小説の『沈黙』だった。この小説が描いたテーマは、日本人だけでなく、世界の人々の胸に響いた。『沈黙』は世界20カ国以上で翻訳されて、刊行から50年を経た今も世界中で読み継がれている。
台湾で撮影、アカデミー賞監督が協力

キリスト教を棄(す)てる宣教師フェレイラは実在しており、若き司祭ロドリゴにもモデルとなった人物がいる。激しいキリシタン弾圧の様子を含めて、史実や歴史書に基づいて書かれた小説であるため、映画化にあたっては、17世紀の日本をどこまで忠実に再現できるかが大きなポイントだった。
完成した映像を見ると、往年の黒澤映画かと見まごうばかりに、当時の日本がリアルに描かれていることに驚かされる。その撮影の舞台裏を知って、さらに驚くのは、そのすべてが台湾で撮られたことだ。
脚本が完成したのは、スコセッシ監督が原作と出合ってから18年後、06年のことだ。そして撮影地を探すロケハンが始まったのは08年。ニュージーランドやカナダなど様々な場所を見て回り、ついに台湾で完璧なロケ地を見つけたという。舞台である長崎と、地形や天候が似ていたのが、大きな決め手になった。
台湾での撮影にあたっては、『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』などでアカデミー賞監督賞受賞歴を持つ台湾出身のアン・リー監督らの協力を得た。司祭たちが海岸の近くを移動するいくつかのシーンは、もともと『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』のために建造された水槽で撮影されたものだ。
過酷な地形や天候に悩まされた撮影

撮影が始まったのは15年1月31日。スコセッシ監督は、できるだけ物語が進む順序通りに撮影したいと望み、実際そのように撮影が進んだ。
司祭たちがかくまわれる村のシーンは、台北から1時間ほどの山岳地帯で撮影された。物語の前半の多くは、山中の小屋や雑然とした場所、泥の中や岩だらけの険しい地形が舞台となる。沼地や急勾配、石が散在する細道での移動に加え、激しく変わる天候がロケ隊を悩ませた。また、映画の冒頭で描かれる雲仙でのショッキングな熱湯責めの拷問シーンは、国立公園にある庚子坪という温泉地で撮影された。100度の蒸気が地面から出ている区域だ。
「映画監督をしてきたなかで、今回の撮影が体力的にも精神的にも最も大変でした。ぜんそく持ちのニューヨーク育ちなので、自然の中に入るだけでアレルギーが出る体質なのです。でも、今回は厳しい場所にもかかわらず、山の中に足を踏み入れた瞬間から喜びを感じました。初めての経験でしたね」と、スコセッシ監督はジャパンプレミアのステージで笑みを見せた。
話の後半に出てくる長崎の街やロドリゴが監禁される牢獄のシーンなどは、スタジオに大掛かりなセットが組み立てられた。こうして撮影は3カ月半にわたり、5月15日に終了。その後、編集作業に実に1年半をかけて、ついに映画は完成した。
困難な環境下での撮影をものともせず、細部にわたるまで徹底的にリアリズムを追求した映像を見ると、監督の執念ともいえる、並々ならぬ原作への思い入れが伝わってくる。
涙を誘った日本人キャストの熱演


この映画にリアリズムをもたらした、もうひとつの重要な要素がキャストたちだ。主人公の若き司祭ロドリゴにふんするのは、『アメイジング・スパイダーマン』のアンドリュー・ガーフィールド、もう1人の司祭ガルペを『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のアダム・ドライバー、彼らの師だったフェレイラを『シンドラーのリスト』のリーアム・ニーソンが演じる。いずれも「スコセッシ監督だから」と出演を決め、当時の宣教師になりきった。
日本人キャストも、素晴らしい演技を見せる。隠れキリシタンが住むトモギ村の長老、イチゾウを演じた笈田(おいだ)ヨシは、パリ在住で俳優、演出家として活躍している世界的な名優だ。イチゾウと同じく、村人のために犠牲になるモキチを演じる塚本晋也は『鉄男』『六月の蛇』などで知られる映画監督。オーディションに臨み、この役に選ばれた。


彼らが、岩だらけの海岸線に建てられた十字架にはりつけにされ、渦巻く潮流にさらされる場面の撮影では、「見ていたアメリカ人も日本人も、キャスト、スタッフが涙しました」と監督は振り返る。「本当に真剣に取り組んだ撮影でした。ひとつの通過儀礼というか、巡礼をしているような感覚を覚えました」。
ほかにも、ロドリゴらを日本に案内しながらも、裏切ることになるキチジローを窪塚洋介、通辞を浅野忠信、井上筑後守をイッセー尾形、キリシタンの村人の夫婦を小松菜奈、加瀬亮が演じて迫真の演技を見せている。

1月17日のジャパンプレミアでは、日本人キャストたちがそろって登壇。俳優をリラックスさせて一番良い状態にして演技をさせてくれると、スコセッシ監督に大きな敬意を払い、過酷な撮影現場だったにもかかわらず、「幸せな時間を過ごさせてもらった」(窪塚洋介)と口をそろえた。
塚本晋也は「私は特に信仰している宗教もないので、スコセッシ教をつくらせてもらいました。監督が望めば、どんなことでもするつもりでした」と言って観客の笑いを誘ったが、ほかのキャストも気持ちの根底は同じだったに違いない。
一方、スコセッシ監督は日本人キャストに対して、「本当にがんばり、力や深みを見せてくれました。どんなにつらい現場でも平然と取り組み、彼らがこの作品の礎(いしずえ)になってくれたのです」と賛辞を惜しまなかった。
米国の俳優も含めて、こうしたキャストと監督の固い信頼関係が、この映画に本物の感情を吹き込んだのだ。
この映画とともに生きている

28年の時を経て、ようやく完成した『沈黙-サイレンス-』。だが、監督は「これで終わりだとは思っていません。自分の心の中に掲げて、この映画とともに生きているという感覚でいます」と言う。
「キチジローが『この世の中に、弱き者に生きる場はあるのか』とロドリゴに問います。この作品は、弱きを否定せずに、受け入れることの大切さを描いています。それは、人が人として生きる事の意味を考えることでもある、と私は思うのです。今は物質的な世界、技術が進んだ世界ですが、そういう世界だからこそ、何かを信じたいという人の"心"について深く考えることが、大事なのではないでしょうか」
渾身(こんしん)の力を込めた1作という名にふさわしい名作の誕生である。
(日経エンタテインメント! 小川仁志)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。