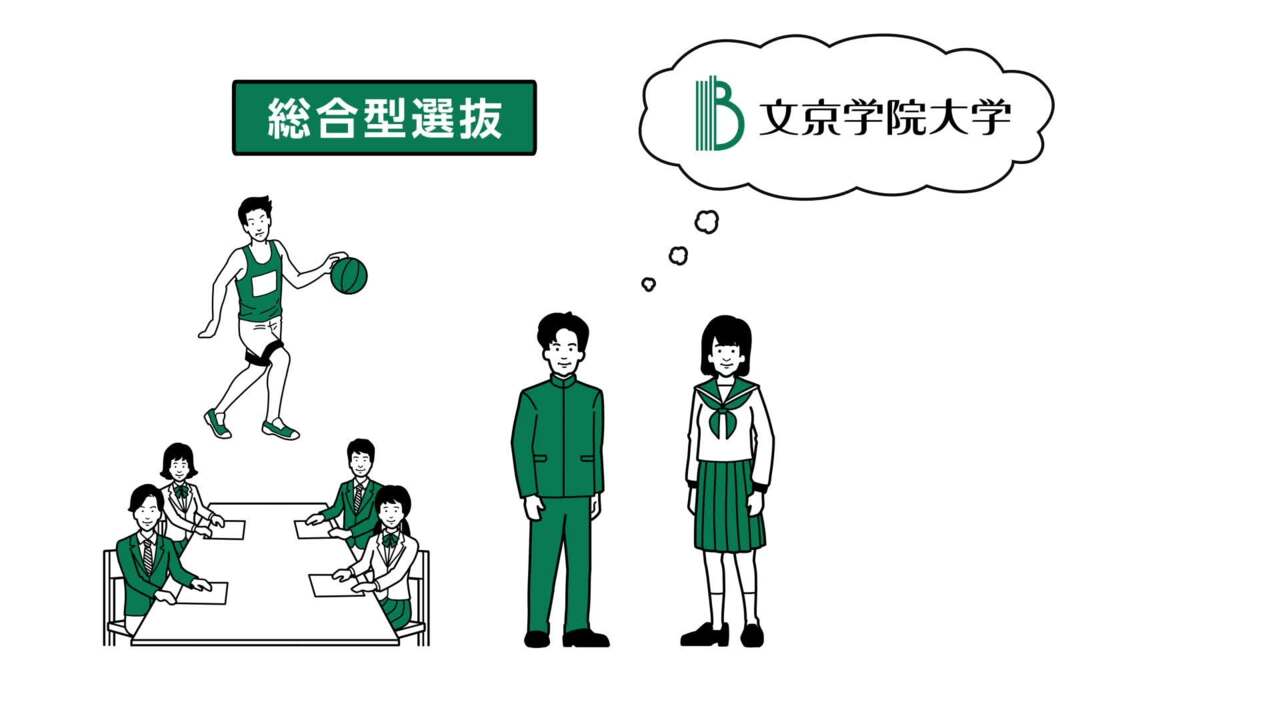■特集:大学新時代
今どきの大学入試や大学教育は、保護者の時代とは大きく変わっています。変化が大きい動きの中から、授業時間の延長や新しい学部、就活のことなど、注目したい6つのポイントを紹介します。(写真=Getty Images)
目次
1.授業時間が1コマ100分以上
大学の授業は1コマ90分が一般的でしたが、2015年度に東京大学が1コマ105分に延ばしたのを皮切りに、100分以上に延ばす大学が増えています。例えば関東学院大学も19年から検討を始め、21年度から授業時間を100分に変更しました。追手門学院大学は、105分授業を21年度から行っています。
高校の授業はだいたい50分ですから、大学に入って100分授業となると、いきなり2倍の授業時間になります。SNSなどでは「90分授業でも長いのに」「集中力が持たない」という学生の悲鳴も上がっていますが、大学側にはどんな意図があり、導入後の変化はあるのでしょうか。

→ もっと詳しく
東大、早稲田に明治、関東学院などで授業時間が「1コマ100分以上」に なぜ長くなったの?
大学の授業時間が105分に延長、学生にはどんな影響が? 校門前で反対ビラを配った教員も
2.「デジタル」「グリーン」、何を学ぶ?
新設する学部・学科に「デジタル」「グリーン」という名称をよく見かけるようになりました。その背景には、国がこの2分野を推進する方針を打ち出し、これらの学部・学科を設置する大学に対して資金的な支援をすることにしたことが挙げられます。デジタル分野は生成AI(人工知能)などの最先端技術を活用でき、グリーン分野はSDGs(持続可能な開発目標)に掲げる環境や食糧問題の解決につながることから、文部科学省は大学・高専機能強化支援事業(成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金)として、こうした人材を育てる大学を支援すると説明しています。どのようなことを学ぶ学部・学科なのでしょうか。
→ もっと詳しく
「デジタル」「グリーン」学部を新設する大学が増加 その背景や理由とは?
3.年内入試の「マッチングサイト」
総合型選抜や学校推薦型選抜といった「年内入試」で合格し、入学する受験生が半数を超えています。総合型選抜は、「この大学に行きたい」「これを学びたい」という意欲や熱意を見る選抜方式です。そのため選考では、ペーパーテストの代わりに志望理由書や小論文、面接などを課します。受験生が高校時代に打ち込んできたことや、その大学が求める学生像(アドミッションポリシー)と受験生が入学後にしたいことがマッチするかなどが、大事です。
そこでホワイトアカデミー高等部が24年にリリースしたのが「年内入試ナビ」です。学びたいことや、将来の職業、大学のエリア、出願&入試条件などを細かく選んだうえで、総合型選抜で希望する選考方法や、自分がアピールしたいことなどを選択すると、自分にマッチした総合型選抜を行っている大学がリストアップされる仕組みです。

→ もっと詳しく
受験生に合った「年内入試」を探す、大学との「マッチングサイト」が登場 偏差値がない新しい選抜を、「スコア化」して判断も
4.スカウト型の就活システム、大学でも
今の学生は、働き方や企業に対する考え方、就活方法が多様化しています。親世代のころとは変化している就活の代表的なものの一つが、「スカウト型サービス」の登場です。スカウト型とは、学生がプロフィルや自己PRなどを登録すると、その情報に興味を持った企業から、会社説明会や面接の案内が直接届くというものです。
このような企業とのマッチングを、独自のシステムで取り入れているのが創価大学です。22年度末にリリースした「キャリナビScout!」は、企業側から学生にオファーできるだけでなく、学生側からも企業へアプローチできるスカウト型というのが特徴です。
→ もっと詳しく
「スカウト型」の就活 大学が企業を厳選、学生からは「安心」の声
5.【インタビュー】合格率3%…ミネルバ大学で得られたこと
14年に開学したアメリカのミネルバ大学は、世界の都市を巡りながら学ぶユニークな教育方法をとっており、「キャンパスを持たない大学」として知られています。WURI(The World University Rankings for Innovation)の「最も革新的な大学ランキング」で3年連続1位になり、世界7都市を回りながらオンラインで授業を行うのが特徴です。
梅澤凌我さん(23)はミネルバ大学に日本の公立高校から進学し、卒業しました。どのような大学生活を送り、ミネルバ大学でどのようなことを得たのか聞きました。

→ もっと詳しく
「ハーバードより難しい」合格率3%…ミネルバ大学とは? 世界7都市を移動、卒業生が語る学生生活
6.大阪・関西万博 大学生が動かす側に
「大阪・関西万博」の開幕(25年4月)が近づいてきました。関西の大学では、学生たちが万博に向けて様々な活動を活発化しています。
関西大学に23年に発足した学生コミュニティー団体は、その名も「関大万博部」。24年春には約120人の学生が新規に入部して部員数が一気に7倍になり、現在は約140人のメンバーがいます。「万博のワクワク感を伝えたい!」との思いのもと、9つのプロジェクトに分かれて活動しています。

→ もっと詳しく
まだ盛り上がってない大阪・関西万博を「動かす側になりたい」 関西大の万博部は部員140人
(文=Thinkキャンパス編集部)
【写真】親の時代と比べて、大学で大きく変化したことは?注目したい6つのポイント
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
DXに貢献できる人材を育成――千葉工業大学に誕生した「デジタル変革科学科」とは
あらゆる産業において急速にDX(※1)推進が求められるなか、千葉工業大学は2024年4月に「デジタル変革科学科」を設...
2025/01/29
PR
-
ミトコンドリアを活性化し、健康寿命の延伸を図る――サプリや治療薬、治療法の研究に打ち込む学習院大学・柳研究室
地球上のほぼすべての真核生物の細胞内に存在するミトコンドリアは、生きていくために必要なエネルギーを産生する細胞小器官...
2025/01/27
PR
-
本に触れ、人と出会い、新たなつながりが生まれる場にしたい。図書館の新たな可能性を広げる創価大学の教職員と学生の取り組み
創価大学開学の7年後の1978年3月に開館した創価大学中央図書館。大学図書館は高等教育と学術研究活動を支える重要な学...
2025/01/24
PR
調べて!編集部
-
子どもの「スマホ依存症」 専門家が教える効果的な予防策とは?
■特集:保護者の悩み・スマホは受験の味方? 受験生といえども、息抜きは大切です。しかし、長時間のスマホの利用は、勉強...
2023/11/26
-
「偏差値が高い大学ねらえるのに…」 中堅大を志望する息子、親のジレンマ
■大学進学お悩みなんでも相談 難関大学を狙える実力があるのに、真剣に勉強をする様子が見えない……そんな場合、親はどう...
2023/06/19
-
-
-
桜美林大学でパイロット体験👨✈️ハッピーフライトteam&グッドラックteamが空に飛び立つ✈️
桜美林大学のHPはこちら! https://www.obirin.ac.jp/academics/aviation_...
2023/06/26
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 教育 - 朝日新聞 2025年 02月 18日
- 「これが経済なんだ!」 小中高生が日常の気づきを動画で表現 2025年 02月 18日
- 打順は全員で一巡、無失点なら守備側に2点 誰一人とり残さない部活 2025年 02月 17日
- 13大学参画の「大学連合」が設立 経済同友会と連携で社会課題解決 2025年 02月 17日
- 益子直美さん「怒ってはいけない大会」10年 常連チームが全国制覇 2025年 02月 15日
Powered by 朝日新聞