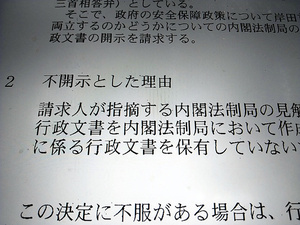敵基地攻撃能力を明記、安保3文書を閣議決定 戦後防衛政策の大転換
岸田政権は16日、国家安全保障戦略(NSS)など安保関連3文書を閣議決定した。NSSは安保環境が「戦後最も厳しい」とし、相手の領域内を直接攻撃する「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」との名称で保有すると明記。2023年度から5年間の防衛費を現行計画の1・5倍以上となる43兆円とすることなどを盛り込んだ。憲法に基づいて専守防衛に徹し、軍事大国とはならないとした戦後日本の防衛政策は、大きく転換することになった。
3文書は、外交や防衛などの指針であるNSSのほか、防衛の目標や達成する方法を示した「国家防衛戦略」(現・防衛計画の大綱)と自衛隊の体制や5年間の経費の総額などをまとめた「防衛力整備計画」(現・中期防衛力整備計画)で構成される。NSSは2013年に安倍政権下で策定され、改定は今回が初めて。
NSSは「我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境のただ中にある」と危機感を強調した。その上で、中国は「これまでにない最大の戦略的な挑戦」、北朝鮮は「従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威」とし、ロシアは「安全保障上の強い懸念」と位置づけた。
こうした安保環境に対応するために防衛力を抜本的に強化していくと表明。「我が国への侵攻を抑止する上で鍵となるのは、反撃能力である」とした。「反撃能力」は「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の3要件に基づき、必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加える能力」などと定義した。岸田文雄首相は16日の記者会見で「相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力となる反撃能力は、今後不可欠となる能力だ」と重要性を強調した。
敵基地攻撃について政府はこれまで憲法上、「自衛の範囲」としつつも、政策判断として能力を保有してこなかった。今回、「反撃能力」と言い換えて保有に踏み切った。ただ、実際には相手が攻撃していなくても、攻撃に「着手」している段階で行使できる。「着手」の認定を誤れば、国際法違反の先制攻撃になりかねないが、判断基準は設けていない。攻撃対象も明示されておらず、歯止めがかからないおそれがある。
◇
〈おことわり〉閣議決定した安保関連3文書で、政府は敵基地攻撃能力を「反撃能力」と表記しています。「反撃」とは攻撃を受けた側が逆に攻撃に転ずる意味ですが、実際には攻撃を受けていなくても、相手が攻撃に着手した段階で、その領域内のミサイル発射拠点などを攻撃することも想定しています。このため、朝日新聞では引き続き、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」と表記します。
防衛費、GDPの2%に
首相は会見で敵基地攻撃は相…