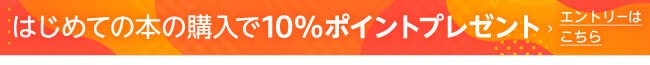無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

読んでいない本について堂々と語る方法 単行本 – 2008/11/27
〈未読書コメント術〉
本は読んでいなくてもコメントできる。いや、むしろ読んでいないほうがいいくらいだ……
大胆不敵なテーゼをひっさげて、フランス論壇の鬼才が放つ世界的ベストセラー。
これ一冊あれば、とっさのコメントも、レポートや小論文、「読書感想文」も、もう怖くない!
- 本の長さ248ページ
- 言語日本語
- 出版社筑摩書房
- 発売日2008/11/27
- ISBN-104480837167
- ISBN-13978-4480837165
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
出版社より
世界の「読書家」がこっそり読んでいる大ベストセラー!

本は読んでいなくてもコメントできる。いや、むしろ読んでいないほうがいいくらいだ――大胆不敵なテーゼをひっさげて、フランス文壇の鬼才が放つ世界的ベストセラー。ヴァレリー、エーコ、漱石など、古今東西の名作から読書をめぐるシーンをとりあげ、知識人たちがいかに鮮やかに「読んだふり」をやってのけたかを例証。テクストの細部にひきずられて自分を見失うことなく、その書物の位置づけを大づかみに捉える力こそ、「教養」の正体なのだ。そのコツさえ押さえれば、とっさのコメントも、レポートや小論文も、もう怖くない!すべての読書家必携の快著。
目次
Ⅰ 未読の諸段階(「読んでいない」にも色々あって…)
1 ぜんぜん読んだことのない本
2 ざっと読んだ(流し読みをした)ことがある本
3 人から聞いたことがある本
4 読んだことはあるが忘れてしまった本
Ⅱ どんな状況でコメントするのか
1 大勢の人の前で
2 教師の面前で
3 作家を前にして
4 愛する人の前で
Ⅲ 心がまえ
1 気後れしない
2 自分の考えを押しつける
3 本をでっち上げる
4 自分自身について語る
商品の説明
著者について
パリ第八大学教授、精神分析家。文学を精神分析に応用する「応用文学」の提唱者であると同時に分析療法の実践家でもある。近著にQui a tué Roger Ackroyd ?(1998;『アクロイドを殺したのはだれか』大浦康介訳,筑摩書房,2001),『失敗作をいかに改良するか』(2000),『バスカーヴィル家の犬事件』(2008)など多数。
大浦康介(おおうらやすすけ)
京都大学人文科学研究所教授。専門は文学・表象理論。訳書にピエール・バイヤール『アクロイドを殺したのはだれか』(筑摩書房,2001),ウォルター・ケンドリック『シークレット・ミュージアム――猥褻と検閲の近代』(共訳,平凡社,2007),ヤン・アペリ『ファラゴ』(河出書房新社,2008)など。
登録情報
- 出版社 : 筑摩書房 (2008/11/27)
- 発売日 : 2008/11/27
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 248ページ
- ISBN-10 : 4480837167
- ISBN-13 : 978-4480837165
- Amazon 売れ筋ランキング: - 399,151位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
お客様のご意見
お客様はこの本の内容について非常に高く評価しています。大変面白い内容で、引き込まれるタイトルで、謎の良書だと感じています。一字一句を丹念に読むのも読書、さらっと流し読みも読書という意見が多くあります。また、本を読むこと、書くことを考えることができると指摘されています。
お客様の投稿に基づきAIで生成されたものです。カスタマーレビューは、お客様自身による感想や意見であり、Amazon.co.jpの見解を示すものではありません。
お客様はこの本の内容を非常に高く評価しています。大変面白い内容で、引き込まれるタイトルだと感じています。また、可能性に満ちた人生を知的に楽しく生きるためのヒントが含まれており、時間潰しとして面白く読めるという意見もあります。著者の意図が書かれており、ジョークや本気という疑問も指摘されています。
"...でいいじゃない。 私はこの本を読んで、読んだことない本についてコメントできるようになりたいなと思った訳ではないが、非常に不思議なタイトルの本だし、最近オススメの本として上がってくるので、なんかクスッとさせてくれるかなと期待して読んでみたのだが全く面白くなかった。..." もっと読む
"最初から最後まで詭弁だけど、時間潰しとしては面白く読めました" もっと読む
"評判通り、大変面白い内容でした。一字一句を丹念に読むのも読書、さらっと流し読みも読書 全く読まずに作品の内容を語る、高等芸術です。お勧めです。" もっと読む
"全くもって引き込まれるタイトルである。そして、ここまで堂々と言い切られてしまうと、本書の中身をきっちりと読みたくなってしまうのが、人の性であろう。ただし、この本はマニュアル本の類ではない。読書に関する常識を問い直し、新しい向き合い方を論じた一冊なのである。..." もっと読む
お客様はこの書籍について、一字一句を丹念に読むのも読書であり、さらっと流し読みも読書だと評価しています。また、テクストを脳にコピペせずに作品の内容を考えるという姿勢が好評です。読書はテクストを脳にコピペすることではないからこそ、これからの読書の手法が変わる可能性があると感じています。
"タイトルからしてふざけてると思いきや、かなり真面目に「読む」ということを書いている。分類、引用、論理の構築までガチでやっている。本に限らず教訓になる点があります。" もっと読む
"評判通り、大変面白い内容でした。一字一句を丹念に読むのも読書、さらっと流し読みも読書 全く読まずに作品の内容を語る、高等芸術です。お勧めです。" もっと読む
"...もっとトンデモ本かと思っていたら、読んでみると意外とまとも。 むちゃくちゃはしょると 読んだ本の内容なんてどうせ覚えていないでしょ ↓ だったら「読んだ」と「読んでない」の境目は無いも同然 ↓..." もっと読む
"面白い。 読書はテクストを脳にコピペすることじゃないからこそだなぁと感じた。 僕たち完読機能も不揮発メモリもないマシンは、いつでも自由に互いを読ん?で語って傷つけ慰めていいと語りかけてくる。 正しさを超えてくための一冊。" もっと読む
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
- 2024年10月3日に日本でレビュー済みAmazonで購入これまで読んだ古典は、あらかじめ知っていたように思えるものもありました。
でっち上げで先に書いたものが、後で当たっていることが頻発していたんです。
無論、金銭も時間も無限ではない。
ショーペンハウアーはエッセイにて。
「本を買うのは結構、同時に読む時間を買えたらどんなに素晴らしいか」
なんて書いていましたが、アマゾンにて「本を読む時間」を速達で買えたら。
やっぱりいいですよね、商品で出して欲しい。
なんて願望を叶えてくれる素敵なジョーク的名著だと思われます。
- 2024年1月25日に日本でレビュー済みAmazonで購入タイトルからしてふざけてると思いきや、かなり真面目に「読む」ということを書いている。分類、引用、論理の構築までガチでやっている。本に限らず教訓になる点があります。
- 2024年11月18日に日本でレビュー済みAmazonで購入タイトルを読んだだけでもそれが分かる。
まだページを開く前なので内容に関しては深く言及しない。今はその時ではないし、もし語るとすればそれなりの時間と熟慮が必要だろう。
だがこの書に大きな価値があることは、30カ国でヒットを飛ばしていること、SNSでも話題沸騰していることからして明らかである。
- 2024年12月4日に日本でレビュー済み邦訳名のような、読んでいない本について堂々と語るだけなら、今なら簡単な方法、インターネットがある。調べればどういう本かはすぐわかる。感想もAmazonのレビューを参考にすればよい。それでも書名を見て興味を持つ人は多いと思われる。それは本だから何か有用なことが書いてあるかもしれないと思うからだろう。
著者はなぜこのような本を書いたか。著者は文学の先生で大学で教えている。本を読むのが好きでないとある。授業の際、色々な本を話題にする。その本を読んでいない場合が多い。そういう読まずにコメントするという経験から、論じてみたとある。著者のような立場の人は少ないだろう。
本を読むべき、は常識化している。ただそう思っても読む気になれない、時間がない。それで読まないまま来ている。そういう人は本書に対して次のような期待が働くのではないか。
1)本をきちんと読まずに内容をつかむ手法等が書いてあるのかもしれない。
2)そもそも本など読まなくてもいいという主張が書いてあるかもしれない。
正直なところこの期待は大して応えられていない。読まないで済ます方法が全く書いていないわけではない。例えば「共有図書館」と著者がいうのは(p.35あたり)、自分で思いついた例では『古今和歌集』について論じるのに『古今集』そのものの精読が必要になるわけでない。『古今集』の前の『万葉集』との関係、後の『新古今和歌集』に与えた影響、それで足りなければ他の八代集との関係を言えればいいのである。本というのはそれだけで孤立しているのでなく、関連する一連の図書との関係が重要だからだ。また「ヴァーチャル図書館」なる言葉が出てくる。(p.194あたり)ある本について話し合う場合、どちらか一方、あるいは双方とも当該図書をろくに知らなくても、議論はできると言いたいらしい。つまり著者の関心は、読んでなくてもコメントできる、批評できるという点である。
本書で著者が一番言いたかったのは、本を読まなくても差し支えない、という消極的、妥協的な意見でない。その前提となっている、本は読むべきという発想を否定している。本なんか読まない方が望ましい、と言いたいようだ。最初の方にヴァレリーがプルーストを読まずに批評して、読んでいないからこそ良い批評になった、と書いてある。これはヴァレリーのような天才だから可能なのであって、普通の者がそれを真似していい批評が書けるか、と思ってしまう。
本書名を見て『吾輩は猫である』の初回で美学者迷亭がする与太話を思い出した人は多いのではないか。読むと驚くべきことにまさに迷亭の話が引用されているのである。迷亭はハリソンの歴史小説『セオファーノ』につき、この小説を読んでおらずに女主人公が死ぬ場面云々とでたらめを言う。苦沙味が相手が読んでいたらどうするのだと問うと、その場合は他の本と間違えたと言えばいいと答える。ここのところで著者は迷亭が答えたように間違いを認めるやり方よりも、でたらめ発言を擁護しているのである。いろんな理屈をこねくりまわして、自分には要約できない。新しい話を創造したので価値があるといいたいのか(そうでもないようだが)。(『セオファーノ』原題Theophano, the Crusade of the Tenth Century; A Novel, by Frederic Harrison、は 実在の東ローマ帝国皇后で10世紀後半の人、テオファーノ。この小説は1904年に出ている。『吾輩は猫である』は1905年(明治38年)から翌年に書かれた。漱石は当時の最新の歴史小説の名を使っているのである。これが本書を読んで、自分としては勉強になったところ)
この著書は理解しにくい書き方をしている。「本など読まない方がより望ましい」という意見をもっと明瞭に分かりやすく主張すればかなり価値のある本になったと思う。本書はいかにも本を読まずに済ませる方法を書いてあるように見せかけ、それを望んでいる読者の興味を引き、内容はかなり分かりにくい。難解な本を高尚だと思う人が結構いるので、それを考えてこんな分かりにくい本にしているなら著者はかなりの策士である。とにかく著者のようなコメントしたり、批評をしたりするという立場ならきちんと本を読まなくていいとは、確かにそうかもしれない。ただ読んでもいない者のレビューなど読みたくもない。
- 2025年1月15日に日本でレビュー済み読むとは一体なんだろうか?
我々は日々本を読む。記事を読む。しかし読みながら同時に忘れなしてゆく。
過去に読んだほとんどの本はその内容を忘れ、もしくは忘れてはいないにせよぼんやりとしか印象に残っていない。
これは、読んでいない状態とどれほど違いがあるものなのだろう。
あるいは世に必読書とされるしかじかの本。アリストテレスから老荘、カント、ユング、ドストエフスキーにサンデルetcetc…それらすべての著作を一か所に並べた時、どんな読書家でも99%は未読の本であるはずだ。
それは、読んでいない状態とどれほど違いがあるものなのだろうか。
違いがないのなら、読まずして語る事もできるのではないか?
できるのであれば…読むとは一体なんなのだろうか?
我々は読むという行為から何を得、何を発信しているのだろう?
本を読むという行為。正確には、「正しく本を読み教養を身に着けるべし」という幻想に一石投じる内容と感じた。
本とはもっと自由に付き合っていいはずだ。何故あれこれの古典名著をちゃんと読んでいるかと互いにチェックしあい、読んでいない本について恥を感じねばならないのか?
無限にうず高く積み上げられた必読書教養書の山を前にして「まだ全部読めていない」罪悪感を抱き続けるのは実にバカバカしい事とは思わないか。
読まなくていいという内容の本でありながら、実際には読書という無限に報われない行為に対する肯定的なメッセージの詰まった一冊だと解釈した。
なんとなれば、本文中に登場するすべてのテクニックはたとえ当該本を読んでいなかったとしても「本自体は大量に読んでいなければ」実践不可能なものばかりだからだ。
ある程度以上読書の習慣がある人間に向けた本であり、普段ほとんど本を読まない人がライフハック目当てにこの本を読んでも内容に共感できず、全く意味不明に映ると思う。
ただ、興味深いテーマではあるが、デマが飛び交いファクトチェックの重要性がいや増す昨今においてはやや爆弾発言の趣もある。
当然ながら、内容を読まずに好き放題デマを発信していいというような趣旨ではないはずだ。
原著の発表が2012年、書かれたのはおそらく2010年前後であり、世界の情報流通環境が今日のように混乱し混沌とした状況と成り果てるギリギリ直前の時期の著作、かつ作者が当時既に60近いネット環境と縁遠い世代の人であった事は頭の片隅に留めておいたほうがいいだろう。
- 2021年12月13日に日本でレビュー済みAmazonで購入知らない時代の知らない人の文章をひたすら引用して、これまで実際に読んでない本についてコメントしてきた著名人がたくさんいたっていう話が延々出てきます。
しかし、そいつらが何者でどういう文脈で何が言いたくて書いた文章なのかを知らない私には全く意味不明だった。
本書は著者が読んでない本の文章をひたすら引用しつつ進んでいきます。実際には読んでないみたいな印を本文に記してるけど、全く意味不明。著者なりのギャグなのかもしれないけどちょっとよく分からなかったな。
1800年代のフランスの詩人や作家に詳しい人ならクスッて笑えるのかもしれないですね。
そもそも、読んだことない本についてなぜ堂々と語りたいのか?その目的自体謎ですよね。
「読んだことないから知らないし、コメントできない。」でいいじゃない。
私はこの本を読んで、読んだことない本についてコメントできるようになりたいなと思った訳ではないが、非常に不思議なタイトルの本だし、最近オススメの本として上がってくるので、なんかクスッとさせてくれるかなと期待して読んでみたのだが全く面白くなかった。私と同じ目的でなんか知的なアプローチで笑わせてくれるのかなという期待で買うならやめといた方がいい。
- 2024年1月2日に日本でレビュー済みAmazonで購入今まで真面目に本を読んできたけれど、これを読んだ後では、本は真面目に読まなくてもいいですよ、と肩の荷が降りた感じすらした。
- 2024年1月26日に日本でレビュー済みAmazonで購入章に分けて、過去の巨人たちが文献をいかに流し読みで、あるいは目次すら触れずに事をなしたかの実例について述べている。そこから得られるのは、本を読むことが目的ではなくその先の悟りにも似た「知性」を得ることが目的であり、その何に対しても備えているかのような「知性」を醸すことができれば目的を達するという逆説的な結論である。
なかなかにへそ曲がりな内容だが、ひろゆき的論破法よりは健全だし、著者は本への敬意を全く失っていない。あなたの読書バリエーションを増すのにきっと役立ってくれる一冊。
もちろんこの本を読まずに堂々と語ってもいい。私のように。