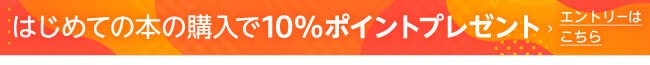新品:
¥1,045¥1,045 税込
ポイント: 10pt
(1%)
中古品 - 非常に良い
¥25¥25 税込

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

「当事者」の時代 (光文社新書) 新書 – 2012/3/16
購入オプションとあわせ買い
本書はその続編に当たる。今回はビジネス論ではなく、ただひたすらその言論の問題を取り上げた。しかし私は巷間言われているような「新聞記者の質が落ちた」「メディアが劣化した」というような論には与しない。そんな論はしょせんは「今どきの若い者は」論の延長でしかないからだ。
そのような情緒論ではなく、今この国のメディア言論がなぜ岐路に立たされているのかを、よりロジカルに分析できないだろうか----そういう問題意識がスタート地点にあった。つまりは「劣化論」ではなく、マスメディア言論が2000年代以降の時代状況に追いつけなくなってしまっていることを、構造的に解き明かそうと考えたのである。
本書のプランは2009年ごろから考えはじめ、そして全体の構想は2011年春ごろにほぼ定まった。しかしその年の春に東日本大震災が起き、問題意識は「なぜマスメディア言論が時代に追いつけないのか」ということから大きくシフトし、「なぜ日本人社会の言論がこのような状況になってしまっているのか」という方向へと展開した。だから本書で描かれていることはマスメディア論ではなく、マスメディアもネットメディアも、さらには共同体における世間話メディアなども含めて日本人全体がつくり出しているメディア空間についての論考である。
- 本の長さ468ページ
- 言語日本語
- 出版社光文社
- 発売日2012/3/16
- ISBN-104334036724
- ISBN-13978-4334036720
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の説明
出版社からのコメント
著者について
1961年生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。毎日新聞記者、月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリスト。『仕事するのにオフィスはいらない』(光文社新書)、『キュレーションの時代』(ちくま新書)、『電子書籍の衝撃』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『2011年新聞・テレビ消滅』『決闘ネット「光の道」革命』(孫正義との共著、以上、文春新書)など著書多数。総務省情報通信白書編集委員。作家・ジャーナリスト。
登録情報
- 出版社 : 光文社 (2012/3/16)
- 発売日 : 2012/3/16
- 言語 : 日本語
- 新書 : 468ページ
- ISBN-10 : 4334036724
- ISBN-13 : 978-4334036720
- Amazon 売れ筋ランキング: - 462,410位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,182位マスメディア (本)
- - 1,612位光文社新書
- カスタマーレビュー:
著者について

新著『レイヤー化する世界』を刊行しました!
紙の本は、NHK出版新書から。
電子本は、セルフパブリッシングによってKindleStoreから。
どちらでもお好きな方をどうぞ!
【私の書籍のコンセプト】
インターネットやコンピュータのテクノロジは、われわれの社会をどのように変容させていくのか? ネットとリアル社会の境界部分ではどんな衝突が起こり、どのようにリアルはネットに呑み込まれ、そしてどのように融合していくのか? その衝突と融合のリアルな局面を描いていくこと。そしてその先に待ち受ける未来ビジョンを、できうるかぎり事実に基づいて描写していくこと。それが私の仕事の基本的なテーマです。
【私のバックグラウンド】
1961年兵庫県の片田舎で生まれ、大阪西成のディープな街・玉出で育つ。
母の再婚相手がトヨタ自動車の工員に採用されたのをきっかけに、愛知県豊田市に転居。地元中学から愛知県立岡崎高校に進学。文学や哲学書に埋没した思春期をすごす。
1981年、早稲田大学政経学部政治学科入学。前半はロッククライミングに熱中し、後半は当時普及しはじめていたPCを手に入れ、パソコン通信を使ったオータナティブな市民運動ネットワークの実験に参加。掲示板での議論に熱中する。
1988年、毎日新聞社に入社。以降12年あまりにわたって事件記者の日々を送る。東京社会部で警視庁を担当した際にはオウム真理教事件に遭遇。ペルー日本大使公邸占拠事件やエジプト・ルクソール観光客虐殺事件などで海外テロも取材する。
1998年、脳腫瘍を患って長期休養。翌年、糸が切れたように毎日新聞社を辞めてアスキーに移籍。月刊アスキー編集部でデスクを務める。
2003年、独立してフリージャーナリストに。以降たったひとりで事務所も構えず、取材執筆活動に邁進中。
カスタマーレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
- 2024年7月28日に日本でレビュー済みAmazonで購入どなたかが?ネットでこの本を勧めてあったので早速購入。
まだ読んでません。
- 2012年10月3日に日本でレビュー済みAmazonで購入「戦後教育」 や 「自虐史観」 などが問題にされるなかで戦後の歴史をふりかえる機会はすくなくないが,それでも,この本はこれまでわすれていた,あるいは気づいていなかった事実に気づかせてくれる. 太平洋戦争後 1960 年ごろまで,一般の日本人は戦争の被害者であり加害者意識がなかったこと,そこでめばえた加害者意識が 「7.7 告発」 というできごとを機会に急速にひろまり,そこからこの本の最大のテーマである 「マイノリティ憑依」 が日本人とくにマスコミなどにひろがっていったこと.
「マイノリティ憑依」 ではアウトサイダーがマイノリティの立場にたとうとするが,東日本大震災ではその規模がおおきかったがゆえに,河北新報の記者をはじめおおくの当事者 (インサイダー) が情報を発信することになった. 著者はそこに 「マイノリティ憑依」 からぬけだす道をみている. しかし,津波被害と原発被害がまったくことなる様相を呈しているように,東日本大震災の被災者ではあっても,ひとによって経験はまったくちがう. 津波被害者は原発被害に関してはアウトサイダーであり,逆もまた真だ. 東日本大震災の被災者であるということだけで,みなが当事者だということにはならないだろう. だから,この本のタイトルには違和感をおぼえる. 「マイノリティ憑依」 が問題点であるのなら,それは今後も継続していくのではないだろうか.
- 2012年4月25日に日本でレビュー済みAmazonで購入素晴らしいの一言。と同時に、読んで痛みを覚えずにはいられない。
巷に溢れる「マスゴミ批判」とは一線を画した、その構造的問題と、それが私達に繋がっていることを浮かび上がらせた渾身の一作。
なぜマスメディアは、自らがエスタブリッシュメントでありながら、存在しない「市民」目線で権力糾弾することをジャーナリズムだと勘違いしているのか。彼らがバカだから?違う。そうならざるを得なかった歴史的な背景があるから。しかしそのままで良いのか。それも違う。彼ら自身もわかっている通り、もはやそうした旧来型の報道では何も生み出さない。ではどうしたら良いのか?
こうした問いに対し、著者は歴史という横糸と、自ら属していたメディアのミクロな日常を行き来して、立体的に私達の思索を深める。
実はこの本を読みながら、私は痛みを感じていた。本書の重要なテーマ「マイノリティ憑依」(幻想の弱者を勝手に代弁し、体制や反対者を糾弾すること)は、実は我々NPO業界にこそ、蔓延しているものだからだ。
私達NPOは、基本的には課題を抱えた人々の課題を解決するサービスを提供する。またそうした課題を生み出す構造を批判する。例えば、ホームレスに炊き出しをしながら、貧困を生み出す社会構造を批判したり、障がい者に働く場所を提供しながら、障がい者が就労しづらい社会を批判したり、というように。これは一見別に悪くないように見える。
しかしこれは「マイノリティ憑依」と常に紙一重の危険性を持つ。例えば私の属する保育業界は、非常に古くからの利権構造が温存されている業界だ。例えば既存保育業界団体は「子どもの目線にたった政策を!」「子どもの育ちが最優先なのに、政府はそれをないがしろにしている」と、我こそは「こども」の代弁者である、という立ち位置からの政府批判を繰り返し、規制を温存させ、新規参入を阻害することで、自らの業界の安定性を保持している。
「子ども」という弱者の立場に立つように見え、しかし現実はそれを自らのイデオロギー(及び利権)を無意識に正当化するツールとしてフル活用している。(しかし彼ら個人個人と話すと、普通の良い人だったりする。)
「当事者を代弁し、社会構造の歪みを是正する」という使命を帯びたNPOには、常にこうした「マイノリティ憑依」化する罠が待ち受けている。
では一体どうしたら良いのか。本書は私達に思考を求め、安易な答えを用意してはいないが、私自ら考えたことを備忘録的に記したい。私自身が幾度もこの罠にはまり、そして今後もその危険性を抱え続けるから。
(まだ十分に練られてはいないが)それはいくつかのフレーズに要約できるように思う。
1.「行政批判」ではなく「新サービス創造」
2.「抽象論」から「具体的対案」
3.「糾弾」から「対話による相互啓発」
1は、安易な行政批判(そしてそれは非常に気持ちいい)を慎み、「だったら自分達でやってみようぜ」というスタンス。これはソーシャルビジネスに通じる。
2は、「これだから日本の政治はダメなんだ・・・」的な抽象的批判を脱し、「この法案の5条にこの文言を入れ込むともっと良い」というような具体的対案。
3はマイノリティを勝手に代弁して誰かを攻撃するのではなく、先入観を排した対話を通じ、いわゆる「弱者」の視点をインストールしてもらえるよう、促しながら、その対話の中で自らも学んでいく、という姿勢。しかし手間も時間もかかるこうした対話には、ITという補助ツールが欠かせない。ソーシャルメディアを介した新たな「対話」手法を開発していくことだろう。
ポスト311をどす黒く覆った、東電(≒政府)不信と原発を巡る相互糾弾社会の出現。こうした社会を主体的個人として生きるために、本書を全ての人々に手にとってもらいたい。本書を読んだ後には、自分は無垢な傍観者で「何でも批判できる」という思い込みは捨てざるを得ない。
そして特に、我々社会問題に関わる人間には、必読の書であろう。代弁する権利という諸刃の剣を手に持つ我々には。
- 2016年4月16日に日本でレビュー済みAmazonで購入戦後日本のマスメディアの言論の構造的特徴を解剖する。
日本人が日本大衆にむけて書く言論。
いまだに日本でしか通用しない言論がまかり通っている。
その言論が どのような背景から うまれてきたのか を 解析、提示する。
ながい時間スパンを射程にいれたメタ言論と思われる。
著者のこれまでの IT関係の本とは異なる重厚な内容。
第一章から読ませる。冗長ではないと私には思われた。
- 2012年3月23日に日本でレビュー済み言いたいことは分かるのだが(共感もするのだが)、論述が回りくどく、概念化や抽象化が稚拙だ。
特に1章2章がつまらない。それで100ページを超えてしまう。読むのをやめようかと思ったが、3章からは面白くなる。
左翼はなぜマイノリティに憑依していったのか。はっきりしているのは、それは別に日本に特殊ではない。米国でも1960年代から「インディアン」などについての文献や映画がふえてくる。サルトルをはじめ当時の代表的知性が第三世界や被抑圧民族に注目し同情し連帯を表明した。その思潮を日本も浴びたということだ。第3章では、そのマイノリティ志向がエスカレートしていく過程を跡付けており、面白い。だが、著者がそれを戦後日本の特殊事情から生まれた思想のように言うとき、その言は的を外している。
今の若者が冷戦の空気を分からないのは仕方ないが、著者の世代で冷戦のリアリティが分かってないのは珍しい。当時の左右両党は裏で手を結んでおり対立は茶番だった、というのは一面の真実だ。だが、実際にアジアの共産化の脅威があり(インドシナでまさに火を噴いていた)、それを本気で恐れる勢力と、それを本気で待ち望む勢力が存在した。左翼がマイノリティに期待したのはその現実性が背景にあったからで、「エンターテイメント」としてではない。
その冷戦下に、日本を含めた西側メディアがなぜ左傾化したか。それは事実であり、また別の問題でもある。米国のベトナム戦争報道のliberal biasが問題視されたのは、むしろ最近(冷戦後)になってからだ。ごく単純に、日米西欧の主要メディアの構成員は国民平均よりも左であった。米国では、主要新聞の記者の6割は民主党支持者で、共和党支持者は2割に満たない。1970年代、おそらく80年代においても、日本で同様の調査をすれば、社会党支持者が自民党支持者を圧倒しただろう。
なぜ、メディアには左翼の人が集まるのか。ニクソンだったかが言ったとおり、「保守の人はもっとまともな職に就くから」だろうか。いずれにせよ、日米のジャーナリストの信条である現代リベラリズムの標準的理解では、マイノリティを尊重するのは自由の核心である、ということになっている。その是非はともかく、ここでも、著者が説くような戦後日本特殊的事情は必要ない。
90年代に、そのマイノリティ志向が、メディアで左翼的記事を書く記者自身にも信じられなくなったさまを、著者は自らの体験として書いている。それは単純に、この時代になれば、外の世界と同様、メディア内にも左翼が減ったからだろう。だが、著者は左翼のインナーサークルでないから分からないのだろうが、都知事選のたびに石原慎太郎をなんとか落とそうというような策動は細々とある。左翼偏向がなくなったわけではないから、著者の言うマイノリティ憑依がまったくポーズだけというわけでもない。
本書はおそらく、時代遅れの左傾メディア批判を書こうとして書き始められたのだろうが、主題と関連の薄いエピソードに深入りし、精神史や思想史にずれ込み、擬似社会学的議論に流れ、全体としてとりとめのないものになっている。引用文が地の文と分かりにくいなど編集的不手際もある。電子書籍の普及で、編集者不要論が唱えられるが(そして著者もそれに共感しているように思われるが)、皮肉なことに、ちゃんとした編集者が介入すればもっといい本になったのに、と思わせる実例になった。
- 2013年1月19日に日本でレビュー済みAmazonで購入新聞記者時代の夜回りなどの記者たちの慣習については
とても面白い。第二章以降の「幻想としての「市民」」みたいな理論は
文化人が好きそうな話ですが、社会学部の大学院の研究論文って感じですね。
佐々木さんの社会学研究科の修士論文(仮)といった意味合いでしょうか。
- 2012年11月30日に日本でレビュー済みAmazonで購入目次がない。図が見れない。章の変わり目で改ページされていない。改ページしないなら、せめて章の見出しを太字で強調して目立つようにしてほしいです。
ページ数が多い本を無理やりひとつのファイルに詰め込んだからたからこんな変なことになってるんだったら、上巻と下巻のふたつにわけたほうがよかったのではないでしょうか。
- 2013年12月11日に日本でレビュー済みAmazonで購入佐々木俊尚さんの本は、どでも「なるほどー」と思いますが、
この『「当事者」の時代』は、佐々木さんの毎日新聞時代の経験が詳細に綴られていて、
とても面白かった。
新聞の世界って、メディアって、政治の世界って!!!
と、まるで小説を読んでいるよう。
日本人の「空気の読み方」と「同調圧力」について、考えさせられました。