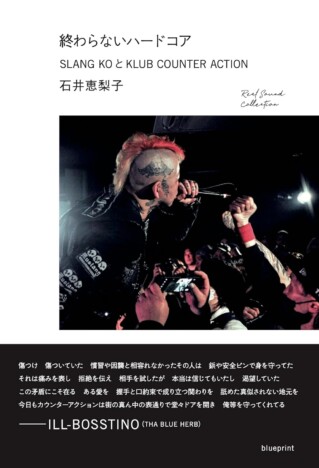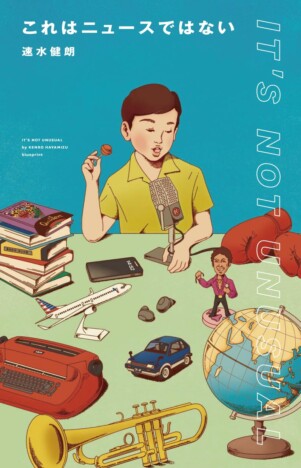米津玄師が讃える無邪気で若いエネルギー 「Plazma」は2020年代ボカロミュージックと向き合った1曲に
「Plazma」というタイトルも興味深い。米津は過去に「春雷」や「感電」といった、雷や電気に関連したタイトルの楽曲を作っている。歌詞でも〈稲妻の様に生きていたいだけ〉(「感電」)と歌ったことがあった。「Plazma」というタイトルはそうしたセンスに通じるものだが、これまでのタイトルには電気的なイメージとともに、痛みを伴った緊張感があるのに対して、〈プラズマ〉という言葉には、エネルギーを持った何かが発光していたり、目に見えない何かがすばやく振動しているようなイメージが含まれているように思う。もちろん人によって差はあるだろうが、なんとなく明るく光っていて、周りからの力に影響されない強いパワーを感じる言葉だ。
また、曲中で〈プラズマ〉という言葉は〈目の前をぶち抜く〉ものでもある。サビ頭では〈飛び出していけ宇宙の彼方 目の前をぶち抜くプラズマ〉と願うのようにして歌われる。「ある種の無邪気さ」が宿ったというこの曲において、サウンド面だけでなく、歌われているものにもその「無邪気さ」があるように思う。若さゆえのスピード感やパワー、宇宙の果てまで飛び立たんとする得体の知れないエネルギー。「Plazma」はそうしたものを讃える歌に聴こえるのだ。
ほぼ一人で制作したことで、彼の頭の中で起きていることが、いわばそのまま音に変換されたと言えるこの曲。音楽を始めた頃の気持ちを呼び戻し、創作にふけるその情熱を音にぶち撒けて、歌詞では〈光っていく〉と高らかに歌い放つ。そんなこの曲の歌詞には、“もう一つの世界線”に思いを馳せる言葉が並ぶ。
〈もしもあの改札の前で 立ち止まらず歩いていれば/君の顔も知らずのまま 幸せに生きていただろうか〉
〈もしもあの裏門を越えて 外へ抜け出していなければ/仰ぎ見た星の輝きも 靴の汚れに変わっていた〉
こうした〈もしも〉を重ねて、今までの人生における選択で、別の道を選んでいた場合の世界を想像する。つまり、ある意味でこの曲は想像力の歌とも言える。今、〈君の顔〉を知らない者も、〈靴の汚れ〉を見ている者も、目の前の選択次第では、宇宙の彼方、どこか遠くへと飛び立てるかもしれない。その“ここではないどこか”へのイマジネーションが、まさに宇宙に漂う星のように音の粒になって鳴り響いているかのようだ。
ハチ=米津玄師の変遷と不変性 「ドーナツホール」と「がらくた」に通じる“欠けたもの”を描く本質
「GODIVA」とのコラボレート商品発売、ならびにそれに伴ったボカロP・ハチ時代の楽曲「ドーナツホール」MVリメイクが公開された…