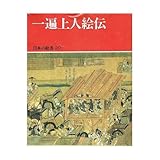(河出文庫)
拙著『〈郊外〉の誕生と死』において詳述したように、一九八〇年代は郊外消費社会が隆盛を迎えつつあった。それは七〇年代にファミリーレストランを先駆けとし、駐車場を備えた郊外型商業店舗、所謂郊外店を増殖させたロードサイドビジネスの急成長によっている。都市の郊外と主要幹線道路沿いに出現したロードサイドビジネスの林立する風景は、次第に全国至るところの郊外に及んでいく。そしてこのロードサイドビジネスはチェーンストアを志向し、連鎖的に出店することでナショナルチェーンを形成する。その店舗の建築様式はCIによって規格化されていることもあり、それは全国の郊外に同様の建物が大量に出現したことを意味し、郊外の風景の均一化を推進する装置のように機能したといっていい。つまりビジネスもそれまでの街路=ストリートから、道路=ロードへとスプロール化していき、郊外化していったのである。

それは一方で、八〇年代が従来と異なる開発の時代であったことを物語っている。すなわち全国の郊外の田や畑、森や林、山や谷が新興住宅地へと変貌していったばかりでなく、ロードサイドビジネスへとも転用され、農耕社会から消費社会へと風景が一変してしまったことにつながっていく。一九八四年に刊行された中上健次の『日輪の翼』も、そのような全国に及んだ開発の動向とパラレルに出現した作品と見なせるだろう。
中上は紀州の被差別部落=「路地」を物語のトポスとして、『岬』『枯木灘』『鳳仙花』『千年の愉楽』などを書き継ぎ、『地の果て至上の時』において、その神話的世界のバックヤードというべき「路地」が土地開発によって解体されてしまった光景を描くに至る。そして『日輪の翼』はその「路地」の解体を前提として始まっている。具体的な「路地」解体の経緯と事情に関しては、『日輪の翼』と同年に刊行された小説とノンフィクションの混住する『熊野集』の中で言及され、それが市と新宮の独占スーパーマーケットによる、山と「路地」の開発に起因し、しかもその工事は中上の親族の営む土建会社に担われたものだったのである。

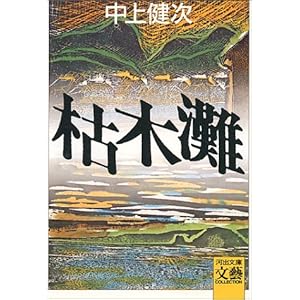




それは原子力発電と高速道路計画を背景にしていたが、「路地」を更地にして新たな道路を通し、スーパーマーケットを建設することで、当然のことながら、その業態はロードサイドビジネス的な郊外型スーパーを目論んでいただろうし、「路地」を一気に消費社会にする開発だった。同時代に起きていた郊外消費社会の隆盛が、その開発を促したことは疑いを得ない。かくしてベンヤミンのいうパリならぬ、紀州の「路地」=パサージュは、道路=ロードに寄り添う消費社会へと変容した。そしてスーパーの出現「路地」の変容は、本連載6 の大江健三郎『万延元年のフットボール』における、やはりスーパー出店によってもたらされた四国の村の変貌を彷彿とさせる。それを考慮すれば、中上の『地の果て至上の時』は、大江の『万延元年のフットボール』に対応しているのかもしれない。なおこの「路地」は『熊野集』が書かれていた間に中上健次自身によって映像として残され、それはこれも本連載 31 の青山真治監督の『路地へ 中上健次が残したフィルム』(スローラーナー、紀伊國屋書店発売、二〇〇一年)に収録されている。


そのようにして「路地」は消滅し、『千年の愉楽』において、「路地」の語り部だったオリュウノオバも死に追いやられ、その他のオバたちも立ち退きを迫られ、熊野を出て、伊勢から東京までノマド的に巡歴を重ねていく物語が『日輪の翼』ということになる。夏の終わりに「路地」の若衆(わかいし)であるツヨシと年長の田中さんは冷凍トレーラーに七人のオバを乗せ、「路地ごと空を飛んでいる」ように高速道路を走っていく。そのトレーラーは運送会社から盗んだもので、改造して満艦色の照明とスモールライトを施していた。もはや戻るべき「路地」もなく、仏壇まで入れた鉄の魚くさいトレーラーは、まさにオバたちがこもるうつほや子宮のようでもあった。
ツヨシは走り出して間もなかったけれど、高速道路のドライブインのところでトレーラーを停め、中にいるオバたちを外へと招く。それは「路地」の山の上にあったのと同じ夏芙蓉の木が「他所の土地の道路脇」、まさにロードサイドに見えたからだ。中上の「路地」をトポスとする物語群にあって、「路地」を象徴する木で、白い花を咲かせ、その白粉の匂いに小鳥たちが群れ集うとされるが、正式の樹木名ではない。その夏芙蓉の木がヘッドライトの灯りの中に浮かんでいる。オバの一人がツヨシにその花を取ってくれと頼む。ツヨシは夏芙蓉の木の梢に登り、七人分の花をオバたちに放った。その木は「境目」を表象しているようであり、「オバらは天の道、走って、山から山へ翔んで来た気」になっていたように、そこは伊勢へと入ったところだった。オバたちは色々な不安と妄想に捉われ、「路地から外に出た途端、道は果てなくなる」ということを実感していた。
そしてキクノオバが「路地」のできる前にあった蓮池のことを話し始める。「路地」はかつて蓮池であり、その清水の湧きでる蓮の花が咲いた池のあたりに、他所から流れてきた夫婦が住みつき、小屋を建て、子供が生まれた。だがその子供は尋常ではなく、「手が三本あったとも四肢が獣のものだった」ともされ、五歳の時に蓮池で水死した。その宿命の子供を育てるために、夫婦は続けて生まれた二人の子供を蓮池の沢の中に埋めて息を断っていた。春になると、蓮は美しい華を咲かせ、夫婦は湧き出る清水を利用し、廃馬のはいだ皮をなめす仕事を始め、それに続いて多くの流れ者が住みつくようになり、蓮池が埋められ、そうして「路地」が形成されたのだ。
これはいうまでもなく、『古事記』(岩波文庫)などに伝えられた国生み神話をなぞり、しかも聖を転倒させ、「路地」の神話と ならしめている。蓮池の夫婦は『古事記』における伊邪那美命と伊邪那岐命であり、生まれた「奇形児」の子供は「葦船に入れて出てき」「水蛭子(ひるこ)」なのだ。しかもこの夫婦が廃馬のはいだ皮をなめす仕事を始めることによって、「路地」が開闢していく。それは万世一系の天皇と被差別部落の起源が合わせ鏡のような関係にあることを暗示させている。そうした意味において、その生誕の「異様に小さな、醜い赤子」というフリークス性によって母親に捨てられ、路地のオバたちに育てられたツヨシもまたオバたちと同様に、「路地」の万世一系の末裔となる。かくして冷凍トレーラーによるツヨシとオバたちの伊勢、一宮、諏訪、瀬田、出羽、恐山を経て、東京に至る方向は、これも逆立するイメージを伴う貴種流離譚となって表出する。サンノオバはいう。「わしらは天の道、翔んで来たんやで、いうたら天女や。(中略)わし、アマの川の織姫やし、天女」だと。それにキクノオバも賛同する。しかしその姿はとても「天女」のようではなかった。

七人の老婆らはお伽話で想像する天女の姿とほど遠かった。乞食と言わなくても七人の粗末ななりの老婆らが養老院から脱け出して、類が類を生んで集団化したようなチグハグな姿だったし、それに年寄特有の潤いも張りもない皺だらけの肌の気味悪さが加わり、この上なく貧弱な醜い人間の群れのように見えた。
それもあって路上で「オカイサン」を炊いて食べたり、伊勢神宮で竹ほうきで玉砂利を掃き、御詠歌を唱えるオバたちは「女乞食」のように見えた。かつてであれば、「媼」とよばれたかもしれない。それは共同体を失った現在の高齢化社会のメタファーのようでもある。だがオバたちは「まれびと」のように、物語の中に存在していることも事実なのだ。オバたちを見た女の子は「イー・ティー」だという。しかし折口信夫が『古代研究(国文学篇)』(『折口信夫全集』第二巻、中公文庫)で述べているように、海の彼方からやってくる「まれびと」は王にして貴種であると同時に差別される芸能者たちであり、また「神」にして「乞食人(ほかひゞと)」であることからすれば、「女乞食」のように見えるオバたちもまた「まれびと」として顕現していることになろう。それゆえにオバたちもツヨシなどと同様に、「路地」からやってきた「まれびと」であり、「老婆らが思い出して話しはじめると、そこは路地になる」のだ。
そのオバやツヨシたちの道行ともいうべき各地への巡礼の過程で、オバたちのかつての紡績工場勤めや女郎部屋へと売られた苦難の足跡がたどられ、これも>『枯木灘』で使われた「哀れなるかよ、きょうだい心中。兄は二十一、妹は十九」と歌われる「兄妹心中」がオーバーラップする。そうした紡績女工や売春の実態は、そのままマツノオバの娘スミコや織姫のタエコに再現され、彼女たちもまた折口のいう「まれびと」を迎える「水の女」のような存在である。
それだけでなく、各地の伝説が召喚され、一宮にあっては織姫神話、諏訪においては白馬と甲賀三郎伝説と曼珠沙華譚、瀬田の唐橋では「兄妹心中」の他に、信太妻を彷彿させる狐女房的ララの出現、出羽三山でのマタギたちや恐山におけるイタコたちも登場することになり、そのいずれもが聖と賤を兼ね備えた物語や存在として描かれている。しかしその一方で、ハツノオバは一宮で死に、キクノオバも瀬田の唐橋で姿を消す。蛇足ながら、私は小林清親の弟子の土屋光逸が唐橋を描いた「瀬田の夕照」と題する一枚の版画を一年程前に購入している。

そのようなオバとツヨシたちの冷凍トレーラーによる貴種流離譚は恐山から七八二キロを経て東京へと至り、オバたちは「今まで眠っていた天子様と路地のかかわりを思い出す」のである。そして五人の老婆たちは皇居に向かい、伊勢でそうしたように、皇居前の玉砂利や芝生を掃除し、朝から夜まで皇居を見て、「天子様の体温の伝わる距離に居つづけられると喜び」に包まれていた。蓮池伝説を伴う「路地」から始まった貴種流離譚は『古事記』に基づく万世一系の「天子様」の皇居にたどり着き、オバたちは突然姿を消してしまう。田中さんは皇居を指差していう。「オバら、まさかあそこへ入り込んでいたんと違うじゃろね」と。だがオバたちがいなくなっても、ツヨシと田中さんの旅は続いていくことを暗示させ、『日輪の翼』は終っている。そのツヨシと田中さんの後日譚、オバたちの行方は一九九〇年の『讃歌』へと引き継がれていくのである。

なお本稿とはまったく別に、この二ヵ月ほど、中央公論社版『日本絵巻大成』を繰ることを日課としていたのだが、それらの『一遍上人絵伝』などを始めとする巡歴絵巻物は、『日輪の翼』の物語を絶えず想起させたことを最後に付け加えておこう。