任天堂はなぜ勝者となりえたのか(立命館大学映像学部教授サイトウ・アキヒロ)

※『IT批評 1号 特集:プラットフォームへの意思』(2010年12月刊行)よりサイトウ・アキヒロさんの「任天堂はなぜ勝者となりえたのか」を転載。
任天堂はなぜ勝者となりえたのか
ハードとソフトのシナジーなきプラットフォームはない
もはやハードウェアのクオリティのみでプラットフォーム戦略を勝ち抜くことは難しい。ハードに頼りつづけた日本企業の苦戦の訳がここにある。プラットフォーム戦略における任天堂の成功例は、ガラパゴス化の是非すら問い直しを求める。
躍進の理由を探る
私がゲーム製作に関わり始めたころのゲーム業界は、まだ産業として始まったばかりで、社会的な認知度もなく業界としても試行錯誤な状況でした。そんな中、当時ゲームソフトの開発をしていた岩田聡氏(現任天堂社長)との出会いをきっかけとして、ファミコン初期のころから任天堂のゲーム開発に携わり始め、以後岩田氏プロデュースの元、ディレクターという立場でソフト開発を続けてきました。結果としてその間に任天堂という会社が急成長し、日本発の産業として大躍進していくさまを身近に体感していくこととなりました。
「任天堂躍進の理由はどこにあるのか」。その問いの答えを出していくことは、日本におけるIT製品や家電業界の行き詰まりの根本的な理由を解明すると共に、それを打開する糸口を提示することでもあるのです。
任天堂という企業の閉鎖性
どうも任天堂には「閉鎖的な社風」というイメージがありますが、それが意図されたものであることに気がついている方がどれだけいるでしょうか。グローバリゼーションの名のもとに広く世界に進出して、ワールドワイドにマーケティングリサーチを行う製品開発が当たり前とされている日本企業とは、まったく相容れないモノづくりを自覚して行っていることを認識している方は少ないでしょう。
任天堂を「ゲームメーカー」と思っている方が大半だと思いますが、その本質は「玩具メーカー」です。任天堂が玩具に一番必要な要素と考えているのは『驚き』です。ファーストインプレッションとして「いったいなんだろう」と興味を引き、最終的には「これは面白い」と全身の感覚で感じてもらわなければなりません。任天堂のアプローチを「ブルー・オーシャン戦略」ととらえてもいいかと思いますが、『驚き』の創造という玩具メーカーのアプローチが、誰も思いつかないような独創的な製品を生み出し、結果として「ブルー・オーシャン市場」を創造していると考えた方がいいのです。
そんな任天堂にとって、マーケティングと称して「あなたは何に驚きますか?」と聞いて回ることほど意味のないことはありません。「こんな商品なら驚きます」と言われた時点で誰もが驚く魅力的な商品にはならないからです。
ハード優先のモノ作りの限界
ここにブランド総合研究所の調査データがあります(2010/10/15プレスリリース。株式会社ブランド総合研究所・デジタル家電ストレス調査)。過去1年間(2009/10〜2010/9)に、購入したデジタル家電製品5製品(薄型テレビ、Blu-rayディスクレコーダー、PC、携帯電話、デジタルカメラ)について尋ねたところ、「不満・ストレスを感じる」と回答した割合は5製品合計で49・8%。具体的な不満点では、「電源起動・終了に時間がかかる」「使わない機能がたくさんある」が上位にあがりました。同研究所では「機能が多すぎるがゆえに、使わない機能がたくさんあるという多機能化の現状に対してのストレス・不満が高い傾向にあることが分かった」としています。
たしかに最近の家電製品の機能追加競争はいきすぎといっていいでしょう。本来は快適さを実現するはずの「機能」が、「使いこなせないというストレス」になっているのです。ましてやこの機能追加のために価格が高くなり、メーカーも苦しんでいるのですから、本末転倒もいいところです。こうなってしまった根本的な理由は2つ考えられます。ひとつは戦後、電子立国日本として成功してきた企業体質がいまだにあり、「ハード優先のモノ作り」が主流であること。もうひとつは「他社が追加した機能はわが社も追加しなければ」という呪縛にも似た考え方です。
江戸時代まで遡れば日本はソフトウェアの国でした。しかし開国以来の西洋からの文明開化の流れの中で、その技術格差を埋めるべくハード志向になり、終戦後の復興もその流れの中で邁進してきた経緯があります。しかし人件費等の理由でその優位性がアジアに奪われた今、いま一度ソフトウェア志向を見直す時にきているのではないでしょうか。
ソニーのプレイステーションは、当初スーパーファミコンに拡張機器として接続するCD-ROMシステムとしてスタートしたのですが、最終段階で両社は決裂しました。私はこれを、ソフトを重視する任天堂と、あくまでもハード志向のソニーとの決別であったと考えています。
プレイステーションの登場後、ハードの進化とゲームの面白さがシンクロしていた時代はソニーが市場を席巻しましたし、任天堂がソニーを追いかけていた時もありました。本稿のテーマとは異なるため詳細は次回に譲りますが、ハードの進化とゲームの面白さが飽和状態に陥った時、さらなるハードの進化でゲームの深度を深めていくソニーと、『驚き』の論理でおもちゃの基本に戻った任天堂とで、方向性が大きく分かれていくこととなります。
ファミコン、スーパーファミコンで急成長していた時、任天堂の山内社長は当時、以下のようなコメントをしています。「ユーザーはハードではなく、ソフトをもとめている。ソフトを遊ぶためにしかたなくハードを買う」「ソフトウェアに開発のコツはない。説明できないからソフトウェア。説明できるのはハードの世界」「意見や考え方は言ったがファミコンは私の号令一発で作ったのではない。それはハード志向の見本のような考え方。あえていえば、任天堂という企業の体質がファミコンを作った。ソフトウェア作りはシステムではない、体質である」と。
ハードとソフトの徹底的なシナジーを追求
任天堂は玩具メーカーであると先に述べましたが、玩具開発はハードとソフトの徹底的なシナジーを追求することが前提です。新しいテクノロジーというハード的なもので「おやなんだろう」と興味を誘発させ、実際に遊び始めてからは、五感に訴える楽しさというソフトとしての面白さが必要となります。もともとハード・ソフトの作業分担という意識すらなかったのです。山内社長(当時)が「任天堂の体質」といったのはこのことで、こうした社風は岩田社長になってからもモノ作りのDNAとして脈々と流れています。
iPhoneの成功を見た日本の技術者は「技術的には何も新しくない。すぐにでも作れる」と口を揃えて言います。しかし同じようなものが市場に出てきた時、その操作感の悪さに皆閉口しました。触っていて全然気持ち良くないのです。
日本の家電の作り方は、まず仕様書をつくって、その設計図通りに製品を組みあげていくスタイルが主流ですが、それではiPhoneのような心地よい操作感は、決して実現できません。たとえば「設定」画面で上下に移動させた時、指の勢いが強くてちょっと行きすぎてフッと戻ってくる感じ。タイマー設定で時間を送る時の指の動きと時間送りのダイアルが気持ちよくシンクロする感じ。こういった「いい感じ」という曖昧な感覚は、仕様書に書けるようなものではないからです。
ある程度組みあがった実機を実際に触りながら、ちょっとでも指の動きとソフトの動きに違和感がある場合、その理由がハードの性能に由来するのか、ソフトのプログラムの問題なのかと、ハードとソフトの両面から幾度も検討し、粘土を捏ねるようにして作らなければ実現することはできません。そこには機能優先でもなく、デザイン優先でもない、本来の意味でのユーザー目線でのモノ作りが求められているのです。
意識的な鎖国体制
任天堂の閉鎖性は意識的であると最初に述べましたが、ある任天堂のキーマンはこう言っていました。
「我々は意識して鎖国をしている」と。
モノ作りとは本来、それが独自路線であればある程「本当にこれでいいのか」という自問自答の戦いとなります。しかし、その際に開放的に広く情報を収集すると、どうしても競合他社の動きが気になります。そのため、本来自分たちが目指していた方向性に揺らぎができてしまい、自信を失ってしまうかもしれません。その対策としてあえて情報を遮断することで、自分たちの信じる道を進んでいるのだと。その結果がニンテンドーDSであり、Wiiなのです。
ゲームといえば「十字キーといくつかのボタン」が当たり前と考えられていた時、ニンテンドーDSやWiiは、発表時にその目新しさから注目は集めたものの、「キワモノ」的な扱いも見られました。しかし製品が発売されてからの状況は皆さんが知るとおりです。
他社との機能競争などに陥ることなく、独自のアイデアによる製品を創造し突き進んでいくために、あえて情報を遮断する「アンチグローバル」というアプローチ。日本もかつては鎖国をすることで「茶道」「歌舞伎」「浮世絵」といった世界に影響を与える文化を熟成させていったのです。このアンチグローバルによるモノ作りの姿勢は大いに参考になるのではないでしょうか。任天堂のハードとソフトの徹底的なシナジーによるモノ作りの文化は、極めて日本的な職人技のモノ作りなのです。
実は任天堂は最初から閉鎖的であったわけではありません。過去の失敗の教訓から閉鎖的な道を選択していったのです。ソニーとの共同プロジェクトの失敗だけではなく、BS第5チャンネル・セントギガで配信された「サテラビュー」の失敗、リクルートと組んで行った「ランドネット」の失敗。すべては欧米的なグローバルスタンダードがしみ込んでいる体質の企業と、極めて日本的でアンチグローバル体質の任天堂との、モノ作りへのアプローチの違いが本質的にかみ合わない事がその原因でした。
ただし鎖国するだけではありません。「長崎出島のように少しだけ開いて、必要な情報だけを入れていく」。そこが長年のノウハウなのだと、先のキーマンは答えています。
判りやすいアプローチと
判りにくいアプローチ
それでは欧米的なモノ作りとはどういうことなのでしょうか。それは製品のセールスポイントが明快で判りやすいということで、最先端 、高性能、多機能などがまさにそれです。たとえば開発期間が1年、開発予算が1億円で、10の機能が搭載できるとしたら、そのすべてを盛り込む。そのほうが製品の発表会などでセールスポイントが判りやすい。しかし、それだけに他者との競争が激化するため、常に技術革新に邁進しなければならず、ユーザー視点を忘れて技術者の自己満足に陥りやすくなります。
また機能競争によってむやみな多機能化が進んでしまい、ここにもユーザー目線が抜け落ちてしまう。製品ニーズを探るべく広くワールドワイドにマーケティングを行っていくわけですが、広く大多数に意見を求めるということは均一化した製品になりやすいということでもあり、すべての製品がどこか見たようなものになってしまう。そこで差別化のためにさらなる多機能化に拍車をかけていくこととなり、結果として「使わない機能がたくさんある」というストレスに繋がっていくわけです。
かつての家電は生活必需品でしたから、多少使いにくくてもユーザーは使ってくれましたが、現在のように必要な家電がいきわたってしまった状況で、どれも似たようなものであり、かつ使い勝手の悪い製品など売れるはずもないのです。任天堂の場合、1年、1億で製品を開発して10の機能が盛り込めるとしても、まずユーザー目線で本当に必要と思われる機能5つに絞ります。そして、その5つの機能が心地よく使えることに半分の時間と予算を使うのです。できた製品は売りポイントが5つしかなく、その5つにしても体験として使い込んでみなければ良さは理解されません。要するに製品発表会などでは理解されにくいアプローチなのです。
このことが製品発表会などでマスコミを常に困惑させる理由ともなっています。しかし、それが自覚して行われていることは任天堂のCMをみれば明らかです。すべてのCMは製品の特徴や機能を押しだすものではなく、誰か(タレント)がその製品を触って楽しんでいるものしかありません。これは自社の製品は「使ってもらうことでしか、その良さはアピールできない」ということを知っているからです。
今はユーザーも賢くなっていて、製品の印象やカタログだけで商品を買うようなことはしません。ましてや機能自体がなんだかよくわからない物になっているのであればなおさら、インターネットによるユーザーの意見や口コミなどを参考にして製品購入を決めていることでしょう。そうなると重要なのは本当に必要な機能が快適に使えるかどうかなのです。触れるということ自体が心地よい、触っていて居心地がいいから何度も触りたい、言い換えればインタラクティブ(双方向)ということ自体が楽しい、ということがいまの製品に求められているのであり、それを実現するにはハードとソフトの徹底的なシナジーを追求しなければ不可能なのです。
現在の日本のIT、家電メーカーはそれができる体制になっておらず、これこそが任天堂が他社との連携に失敗してきた理由そのものなのです。
ゲームニクスとは何か
ここまでは任天堂の会社としてのアンチグローバルな体質が、誰も思いつかないような独創的な製品を生み出し、結果として「ブルー・オーシャン市場」の創出を可能にしてきたことを述べてきましたが、ここからは具体的なソフト作りへと視線を変えてみます。
任天堂の製品の〝手触り感の良さ?を実現させているのが「ゲームニクス」というノウハウです。マニュアルを読まなくても直感的に操作ができて、思わず使い込みたくなってしまう、そんな方法論を試行錯誤のうえ、長年かけて蓄積してきました。
よく「子供がゲームを始めると何時間も夢中になり、なにも手につかなくなって困る」というお母さんの言葉を聞きますが、なにも「ゲーム」という「魔物」めいた物がそこにあるわけではありません。「人を夢中にさせるノウハウ」が詰め込まれている結果であり、そのノウハウが「ゲームニクス」(GAME-NICS:ゲームのエレクトロニクス、ゲームを作る上での技術という意味の造語)なのです。
スーパーマリオクラブというチェック機能が
ユーザー目線でのモノ作り体質を作った
もともとゲームというメディアはアメリカで誕生しました。1971年、「PONG」というアーケードゲームがヒットして市場が生まれ、197 7年にアタリ社から発売された「ATARI 2600」というカセット交換式の家庭用ゲーム機は1982年の段階でアメリカの4家庭に1台という驚異の普及率となり、ゲーム市場が確立しました。日本のファミリーコンピュータ(以後ファミコン)の発売が1983年ですから、ずいぶん前のことになります。しかし当時5億ドルとまで言われたゲーム市場は1985年に突然崩壊します。経済用語として「アタリショック」と言われた事件です。
1983年にファミコンを発売し、1985年の「スーパーマリオブラザース」の発売によって大ヒットとなっていた頃、任天堂はファミコンのアメリカでの販売を検討していました。そこで任天堂は「アタリショック」の原因を独自に分析し、「アタリショック」の最大の原因は粗悪なソフトが大量に市場に出回ったためと判断したのです。そこで社内に作られた組織が「スーパーマリオクラブ」でした。
スーパーマリオクラブには、老若男女・ゲーム初心者からマニアまで、200名程度のユーザー代表がアルバイトとして登録されています。ソフトが出来上がるとスーパーマリオクラブの中から選出された20名ほどにA4一枚程度の説明書だけを渡してゲームをしてもらい、最終的に点数がつけられます。この点数が「80点以上でないと、自社タイトルについては発売しない」という縛りがかけられたのです。あらゆるユーザーに「良い」と言ってもらわなければならないわけですから、ゲームディレクターにとって脅威的なことでした。本当にお客さん目線で作らなければ高得点は得られないため、ゲームクリエーションの中での「作り手のエゴ」は全く通用しなくなったのです。
スーパーマリオクラブはソフトの品質を管理するためにスタートしたのですが、この審査過程の中で任天堂が発見していったのは、「ゲームの面白さも重要だが、それと同等に操作性が大切である」ということでした。どんなに面白いゲームでも「なにをしたらよいかわからない」「どう操作すればよいかわからない」では、誰もゲームを続けてくれず、ゲームの面白さに到達する前に止めてしまうからです。
マニュアルを読まなくてもプレイできてしまう、段階的に攻略法を学習してクリアできてしまう、長時間にわたって集中してハマってしまう││こういったユーザー中心主義の優れた操作性の方法論が何十年間にもわたって蓄積していくことになります。これが「ゲームニクス」というノウハウなのです。社長が岩田氏になってからは特にこの「ゲームニクス」という点に注力して製品を開発していますので、「DS」や「Wii」の成功もこの基本姿勢によります。
ゲームニクスは
「日本のおもてなしの文化」の集大成
ゲームニクスは概念ではなく、具体的な技術書であり詳細なチェック項目を持っています。その内容は大きく5要素あり、それぞれに細分化した構成となっていますが、概要を知っていただくために、以下に第二項目まで列記します。
1 直観的で快適なインタフェース
A 操作と入力の基本理論
B 入力デバイス特性に対応したUI設計2 マニュアル不用のユーザビリティー
A操作誘導の画面情報
Bマニュアルの組込みとその提示方法3 はまる演出
A ゲームテンポとシーンリズム
Bストレスと快感の バランス
C発見する喜び
D意欲を持続させる仕掛け
E音楽理論の導入4 段階的な学習効果
A 目標設定
B最初にレベルによる振り分けをする
C段階的に難しくしていく
D選択肢や行為を増やす
E習熟度による展開分岐5 リアルとバーチャルのリンク
A 内部化と外部化
Bリアルの抽象と誇張
Cプレイデータの活用
Dライフログの活用
*1
これらの項目の下にさらに小項目が連なっていて、全600項目からなるツリー構造を有した構成となっています。
こうした内容の原点は、茶の湯に代表される極めて日本的な価値観である「おもてなしの文化」に由来します。人を夢中にさせる「ゲームニクス」とは、常にプレイヤーの先回りをしながら押し付けがましくなくさりげないサポートの集大成なのです。人を迎え入れて快適な時間を提供するには「相手に気付かれてはならない」という作法があり、これ見よがしの歓待の演出といった押し付けはユーザーの自由や利便を損なわせてしまいます。あくまでも受け身であるユーザーを主体として招き入れ、常に前向きな感覚で製品に臨んでもらわなければならない。まさに「究極のおもてなし」です。
企業トップの哲学が製品作りのカギとなる
ゲームニクスとは、モニターの中の世界とモニターの外側の我々とをストレスなく繋げ、効率よくプレイヤーに情報を伝達するためのノウハウともいえます。スーパーマリオクラブで培ってきた徹底的したユーザー目線で、モニターの中の臨場感ある世界をいかにダイレクトにユーザーに伝え、いかにデバイスを通してユーザーの感情をモニターの中に反映していくか、そしてこの情報の循環性をいかに高めていくべきか。それにたいしての解答なのです。
ボタンだらけのリモコン、分厚いマニュアル、操作性の悪い画面デザイン。そこにはユーザー目線が全く感じられません。どんなに革新的な技術でも研究者のエゴの押し売りではユーザーには届きません。一般のユーザーにとって一番大切なのは、先進性ではなく、必要な機能をストレスなく快適に使えることなのです。そして快適に使ってもらうために重要なのがインターフェイスデザインであり、 手触り感の良い操作感ということになります。ゲームニクスという操作性のノウハウは決して日本ローカルなものではありません。30年もの間、日本のゲームで世界が遊んでいるのですから、すでに世界スタンダードとなっているのです。
しかしその実現のためには、ハードとソフトの分業や仕様書優先のコスト管理とモノ作りという制作体制そのものを変える必要があります。それは会社の体質そのものを変えることでもあり、そう簡単に実現できるものでありません。
そこで重要なのが会社トップの判断です。「ハードとソフトの徹底したシナジーの実現」はトップの哲学があって始めて成立するものなのです。アップルにそれが出来ているのもスティーブ・ジョブズというトップに権限が集約していることが理由ですし、任天堂があれだけ大きな規模の企業になったにもかかわらず、トップの陣容が何十年もほとんど変化していないのは、かつて小規模であった頃のモノ作りの企業体質を維持するためでもあります。
企業トップの確固たる哲学がなければ、機能を絞ったうえでの手触り感の良い製品づくりは不可能といっても良いでしょう。しかしインタラクティブを主体とした製品であれば、日本文化にはそれができる下地があるのです。任天堂の躍進と成功はそれを示しています。
世界は日本発の快適なIT商品を待っているのです。
*1「IT批評」創刊1号の掲載記事から一部を改変しています。
※『IT批評 1号 特集:プラットフォームへの意思』(2010年12月刊行)よりサイトウ・アキヒロさんの「任天堂はなぜ勝者となりえたのか」を転載
『IT批評』
http://shinjindo.jp/contents/it.html [リンク]
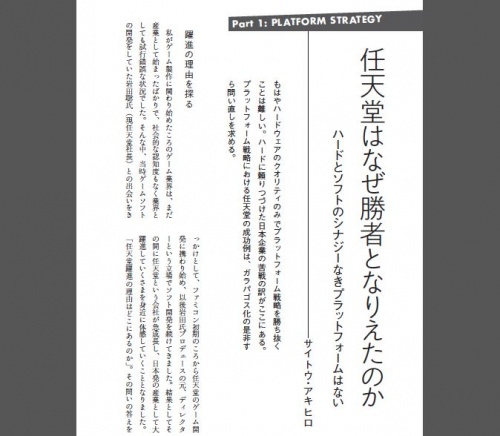
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。















