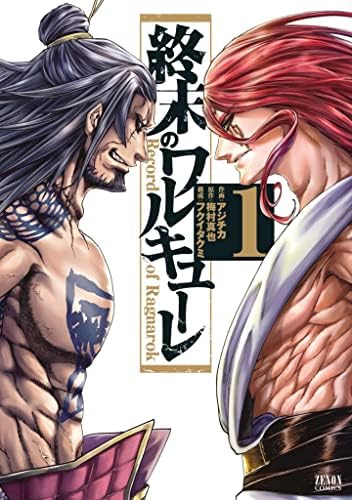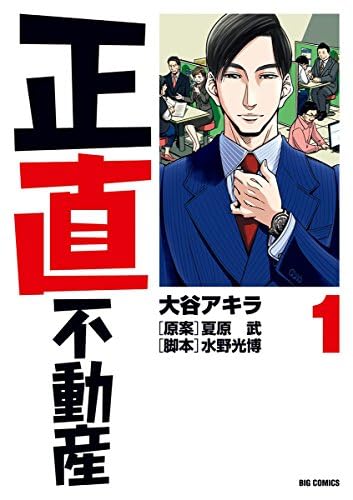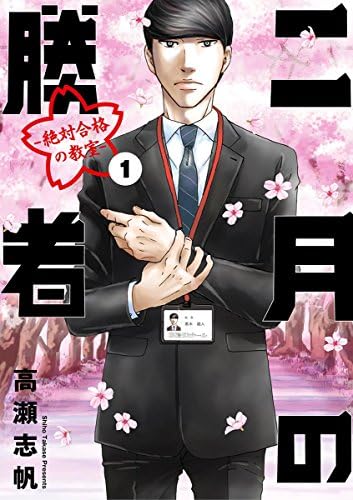大学の資料用に購入致しました。注文して直ぐに届きました。レポート作成には必需品の参考文献なので今月中には読破してレポートを仕上げたいと思っています。この手の本は若干価格が高いのが気になります。電子書籍化してもう少し安く購入出来ると嬉しいです。
¥968 ¥968 税込
| 獲得予定ポイント: | +10 pt (1%) |
上のボタンを押すとKindleストア利用規約に同意したものとみなされます。支払方法及び返品等についてはこちら。
これらのプロモーションはこの商品に適用されます:
一部のプロモーションは他のセールと組み合わせることができますが、それ以外のプロモーションは組み合わせることはできません。詳細については、これらのプロモーションに関連する規約をご覧ください。
を購読しました。 続刊の配信が可能になってから24時間以内に予約注文します。最新刊がリリースされると、予約注文期間中に利用可能な最低価格がデフォルトで設定している支払い方法に請求されます。
「メンバーシップおよび購読」で、支払い方法や端末の更新、続刊のスキップやキャンセルができます。
エラーが発生しました。 エラーのため、お客様の定期購読を処理できませんでした。更新してもう一度やり直してください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

日本の近代とは何であったか-問題史的考察 (岩波新書) Kindle版
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
政党政治を生み出し,資本主義を構築し,植民地帝国を出現させ,天皇制を精神的枠組みとした日本の近代.バジョットが提示したヨーロッパの「近代」概念に照らしながら,これら四つの成り立ちについて論理的に解き明かしていく.学界をリードしてきた政治史家が,日本近代とはいかなる経験であったのかを総括する堂々たる一冊.
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2017/3/22
- ファイルサイズ3.0 MB
販売: 株式会社 岩波書店
登録情報
- ASIN : B073PQMVQG
- 出版社 : 岩波書店 (2017/3/22)
- 発売日 : 2017/3/22
- 言語 : 日本語
- ファイルサイズ : 3.0 MB
- Text-to-Speech(テキスト読み上げ機能) : 有効
- X-Ray : 有効
- Word Wise : 有効にされていません
- 本の長さ : 293ページ
- Amazon 売れ筋ランキング: - 218,787位Kindleストア (Kindleストアの売れ筋ランキングを見る)
- - 1,627位岩波新書
- - 1,901位日本史 (Kindleストア)
- - 4,723位日本史一般の本
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4つ
5つのうち4つ
107グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2020年12月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入著者自身が「意図したところより内容的に平凡であり、むしろ平凡であることがその長所の一つ」との述べているように理解しやすかった。維新以来わが国は、西欧にならい議論による統治と追いつき追い越せの殖産興業ー富国強兵を進め、これを下支えしまた規制するため、権力によるの思想統制のため天皇制を強化していった。と私は理解した。
- 2019年12月23日に日本でレビュー済みAmazonで購入〇青年期の学問と老年期の学問がある、と著者は言う。青年期は業績主義にならざるを得ない。老年期は青年期の業績を超えることはできないが、その反面総論を書くのにふさわしい。本書はその総論の試みである。自分の人生は(学問人生も含めて)凡庸であり生きたこと自体が成果のようなものだが、老年期にこのような本を書いておきたいと考えていたとのこと。あとがきにある記述だが、共感を覚えた。
〇さてその試みが成功しているかどうかは別として、読者としては期待を裏切られたと感じる。問題はタイトルにある。書名は魅力的だ。各章のタイトルはもっと魅力的だ。①なぜ日本に政党政治が成立したのか、②なぜ日本に資本主義が形成されたのか、③日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったのか、④日本の近代にとって天皇制とは何であったか、⑤近代の歩みから考える日本の将来。これらについて、碩学の骨太の議論が読めると期待は膨らむ。しかしその期待はすこし腹立たしいほどに裏切られる。議論の内容が悪いわけではない。タイトルで過大な期待を持たせるからである。
〇以下は、私なりに本書のポイントをまとめてコメントしたものです。ご参考までに。
〇政党政治の成立についての章は面白い。徳川幕府は権力の集中を制限するチェックアンドバランスが強く効いている組織だったらしい(老中などの役職も合議制で月ごとの輪番制だった。大大名等の実力者は幕府の要職に就かず、小藩の譜代が就いた。特定の家臣が将軍を左右しないようにとの配慮らしい。これは韓非子の教えに敵っている)。明治政府にもそれが引き継がれていて、特に明治憲法では、権力の分立と議会制を強く打ち出した立憲主義を取っていた。朝廷に対して徳川幕府のような強い権力が出現するのを防ぐ趣旨だったらしい。その分立の結果、元老院・藩閥をもってしても衆議院は支配できなかった。他方、政党が支配できたのは衆議院だけだった。そこで藩閥と政党の接近が生じて、立憲政友会が起こり、これに対抗する憲政会・民政党が設立された。これ自体は面白い。しかしなぜ日本に政党政治が成立したのかという問いに正面から答えているだろうか?背景と環境の説明に終わっていないか?
〇資本主義の成立となると、もっと腹立たしい。資本主義には、先進技術と資本と労働力と平和が必要だと言い、それぞれがどのようにして実現されたかを説明する。それも大きな山の中を流れるせせらぎを拾って歩くような議論だ。一国の資本主義とはこのような線の細い動きによって成立するものなのだろうか?本当の推進力を見落としているという気がしてしかたがない。
〇なぜ植民地を持ったかは、多少示唆に富む。不平等条約で相手国から搾取すること(植民地と同じ経済的効果を上げることができる)に比べると植民地を持つことは大変なコストがかかった。しかし、植民地を持たないと列強に一等国と認められない現実があったので(大使を交換してこそ一流)一流になるために植民地支配にむかった。しかし日本なりの特徴もあった。それは、経済的権益を求めてアフリカを分割した欧州諸国とちがって、防衛するための緩衝地域として隣接地域を植民地としたことである。
〇天皇制にかかる議論は面白い。憲法における天皇は、合理的な立憲君主であり憲法は自由主義的である(美濃部達夫は戦後も明治憲法改正の必要を感じなかった)が、教育勅語における天皇は、孔子のごとき聖人であり道徳の立法者であり精神的権威である。憲法は高等教育を受けた者しか親しまなかったが、教育勅語はすべての国民が親しんだため、日本人にとっての天皇のイメージは、教育勅語によって形成された。
〇1921年のワシントン体制(3つの多国間条約)によって、国際関係は変わったと著者は言う。それまで列強は二国間条約(例:日英同盟、日露協商、日仏協商など。それも軍事同盟)によって国際関係を形成し、アメリカは孤立的主義的外交路線を取っていた。それ以降は、多国間条約(しかも軍縮条約)による枠組みとなり、アメリカが参加した。それが今日の国際環境に似ていると言いたいようだ。
〇著者は、これからの日本の進むべき道は、国境を超えた市民社会間の協力を促進することによって、国際共同体の組織化を図るべきだと言う。耳に心地良いがほんとうにそんなことか。方向として国際的NGOなどが力を増して行くことはそのとおりだろうと思うが、NGOの正統性の根拠はもろい。少なくとも当面は、多くの事柄が国家の単位で仕切られるのではないか。著者のような議論を横目にしながらも、日々の行政と外交に正しく奮闘する人々が豊富にいてほしいと思う。
- 2017年7月9日に日本でレビュー済みAmazonで購入現代を生きる私たちにとって、「日本の近代」について考察することは、とても大切なことだと思います。
それが、本書を手に取ったきっかけでした。
本書では、序章の中で、日本がモデルとしたヨーロッパ近代を説明するために、19世紀後半の英国人ジャーナリスト、ウォルター・バジェットを引き合いに出します。
彼の著作によれば、「前近代」=「慣習の支配」であり、「近代」=「議論による統治」であるという。
そして、そこから導き出される重要なファクターにより、4つの章が提示されます。
【第一章 なぜ日本に政党政治が成立したのか】
ここでは、江戸時代の藩幕体制の権力抑制的メカニズムに、その萌芽があると指摘しています。
また、明治時代に入ってからも、存在し続けていた「藩閥」も重要な要素です。
【第二章 なぜ日本に資本主義が形成されたのか】
ここでのキーワードは、「自立的資本主義」でしょう。
これを成立させるための条件として、「殖産興業」「租税制度の確立」「労働力の育成」「対外平和の確保」を挙げています。
【第三章 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったのか】
これは、負の遺産ですが、やはり日本の近代を考察するには、欠かせない要素でしょう。
植民地政策の始まりは、日清戦争前後であると分析し、時系列的に植民地支配の状況を解説していきます。
ここでのキーワードは、「地域主義」です。
【第三章 日本の近代にとって天皇とは何であったか】
この問題は、正に日本固有の問題です。
明治憲法起草時、当時の日本人は、「国の機軸」として、ヨーロッパではキリスト教が選ばれていることを知ります。
これに対応する日本の宗教といえば、仏教ですが、「国の機軸」とするには、どうもしっくりこない。
そこで、持ち出されたのが、天皇で、神格化することで、「国の機軸」としたのだそうです。
なお、明治憲法下で発令された「教育勅語」ですが、戦前の天皇の存在と、ある深い関わりがあることを本書で知りました。
本書は、戦前の文書の引用も多く、必ずしも全編読みやすいというわけではありませんが、「終章」で、それまでのまとめのような記述があるので、ここで、頭の整理をすると、理解が深まると思います。
「あとがき」にありましたが、著者は既に80歳を越えており、途中大病をしながらの執筆だったそうです。
それだけに後世に伝えていきたいという思いが伝わる好著でした。
「問題史的考察」という副題の意味を是非とも体感していただきたいものです。
- 2017年6月21日に日本でレビュー済みAmazonで購入明確な座標軸と問題意識のもとに展開されている、近代日本政治史の論考です。考えさせられることが多く勉強になりました。
当たり前ですが、三谷先生はただ者ではない。同時代に生きられて幸せです。
- 2017年4月30日に日本でレビュー済みAmazonで購入<政党政治>、<資本主義>、<植民地帝国>及び<天皇制>という4つのキーワードを基に、「日本の近代」を総括・分析した類い稀なる出色の論考書。まず、本論に入る前の<序章>が凄い。主に、バジョットの論を引用する形で、(日本が目指した)英国を中心としたヨーロッパの近代を総括・分析しているのだが、その流麗かつ緻密な論理展開(それでいて、筆致は穏やか)によって<序章>だけで満腹になる程に充実している。この<序章>を説明した方が本書の意図を理解出来ると思うので、まずは、<序章>について。
「近代」というからには「前近代」があった筈である。「前近代」は「慣習の支配」の時代であった。そして、「『近代』=『慣習の支配』からの解放」であって、「近代」と「前近代」とを別つものは(進化論などの)「自然学」であるとする。更に、「議論による統治」が複雑系としての「近代」に最も適合する政治形態であるとする。また、ヨーロッパの「近代」が「旧い東(ここでは主にインドを指す)の慣習的文明」から「新しい西の変動的文明」への移行であって、英国はインドを「植民地」化する事によって体現したという構図を提示し、これが英国を中心としたヨーロッパを目指した日本が、「東」にありながら、近隣の東の文明圏を「植民地」化する事を"正当化"した要因であると指摘する。そして、本書の課題を、東アジアにおいて最初で独自の「議論による統治」を創出し、最初で独自の「資本主義」を構築し、最初の(そして恐らく最後の)「植民地帝国」を出現させた日本の「近代」の意味を問うと静かに宣言する。
本論ではこれに応じ、日本において、如何にして東アジアにおいては例外的な複数政党制が成立し、「貿易」の問題を含めて何故「資本主義」が形成され、「植民地」化が何故・如何にして行なわれたのか、そして、ヨーロッパの君主制に"似て非なる"、「日本における天皇制」とは何だったのかを分析・解説する。その詳細を語るには紙幅不足だが、著者の瞠目すべき「interdisciplinary」的な学識及び深い洞察力によって、「近代(明治維新後)」と「前近代(幕藩体制)」との間の"隔絶"よりも、ヘーゲル流の弁証法の香りが漂う"物語性"にも富んだ論考を包括的かつ丹念に積み重ね、「現代」の諸問題へと繋げる辺りは見事という他はない。改めて、歴史上の出来事が1つ々々バラバラに起こる訳ではなく、何らかの因果律によって支配されている事を思い知った。まさに、「今」読みたい出色の「日本の近代」総括・分析の書だと思った。
- 2018年6月15日に日本でレビュー済みAmazonで購入高校の政治経済の教科書のような、概念的で、空疎な文章。これだったら、小林秀雄の文章のほうが手ごたえがあって、哲学者のカントやハイデガーのほうが、強烈なリアリティがある。どうしてこのように手ごたえのない、抽象的な文章を読めるのか、疑問。新聞の記事のほうがまだしもリアリティがある。