一九九〇年代のVシネマの隆盛は前回の三池崇史のみならず、多くの優れた映画監督を輩出させた。青山真治もその一人であり、最初に『Helpless』(九六年)を観て、これまでと異なる郊外のロードサイドの犯罪と物語の萌芽を感じた。しかしそれがさらなる事件と新たな登場人物を伴い、地続きの映画として出現するにあたって、二〇〇〇年の『ユリイカ』(以下映画も小説もこの表記とする)まで待たなければならなかった。実際に『ユリイカ』の主要な登場人物の一人は『Helpless』から召喚されている。
 『Helpless』
『Helpless』そして『ユリイカ』における、神話的ファクターはさておき、主として九〇年代に起きた様々な事件や出来事を淵源とし、それらの中から犯罪や物語が発生するに至ったという構図のもとに組み立てられていると見ていいだろう。だが現在の地点でもう一度この映画を観ると、大いなるカタストロフィの後の物語、すなわちそれは他ならぬ二〇一一年の3・11を経た後の物語のようにも思えてくる。
映画『ユリイカ』の冒頭において、「大津波がくる。いつかきっと……みんないなくなる」という少女のナレーションが聞こえてくる。そこに映し出されているのは海ではなく山だが、そうであるからこそ、何らかの予兆のメタファーのように感じられる。それに3・11を経た後で、この冒頭のナレーションを聞くと、否応なく東日本大震災と原発事故の光景が重なり、浮かび上がってくる。『ユリイカ』こそは、二〇一〇年代にもう一度観られなければならない映画ではないかと、心の中で呟いてしまうのである。
そして直接の言及はないし、時代は九〇年代前半に設定されているけれど、『ユリイカ』の制作は九九年であり、九五年に起きた阪神・淡路大震災とオウム真理教事件、九七年の酒鬼薔薇事件などを不可視のバックヤードとして提出されたと考えるしかない。それだけでなく、〇一年の日本での公開寸前に、九州の少年によるバスジャック殺人事件が起き、もちろん事件と映画は何ら通底するものではなかったのだが、『ユリイカ』との共時的関係を示すことにもなったのである。
それらはともかく、まずは冒頭のナレーションに続く『ユリイカ』の展開をたどってみる。九州の地方都市でバスジャック事件が起きる。犯人は拳銃を持って、乗客たちを見せしめのように次々と射殺し、犯人もまた刑事に撃ち殺される。人質とされたバスの運転手沢井=役所広司もその現場にあって、危うく命を失うところであり、彼の他に生き残ったのは中学生と小学生の兄妹、直樹と梢=宮崎将、あおいだけだった。
このバスジャック事件は三人に大きなダメージを与えた。それは見慣れた日常生活に突然亀裂が走り、死の淵まで追いやられ、その寸前で連れ戻されたような体験でもあったからだ。黄泉の国を体験したかのようであり、『ユリイカ』のクロマティックB&Zというモノトーン画面は、それを象徴しているのではないだろうか。いうなれば、この映画は黄泉の国をめぐる物語とも見なすことができる。
その事件以上に三人に深い傷を負わせたのは、マスコミや周囲の視線だった。沢井は家族を捨て、街から失踪し、兄妹の家庭も母が家出し、父が自殺し、崩壊してしまう。そして直樹と梢は心を閉ざし、残された家で二人だけの世界に閉じこもる生活に入った。
それから二年後、沢井は街に戻ってくるが、時を同じくして周辺で連続殺人事件が起き、彼はまたしても周囲から疑惑の目を向けられ、そのことに傷つく。だが沢井は兄妹が二人だけで、引きこもって生活しているのを知り、彼らの家を訪れ、一緒に暮し始め、そこに兄妹の従兄も加わってくる。
一方で沢井に対する殺人の疑惑は消えず、警察の追及は本格化し、拘置されるが、アリバイが立証され、釈放される。そこで沢井は街を出るために小さなバスを手に入れ、兄妹とその従兄の四人で街を発つ。その四人のバスの旅は、撃ち殺されたバスジャック犯人を伴うもののようでもあり、これが映画の後半に至るまでのストーリーの要約となろう。
ただ映像から判断して、その主たるトポスが郊外であることはわかるが、バスジャックの現場はどのようなところなのか、兄妹の住むログハウスは何なのかといったことへの説明は施されていない。
もちろんこれらは当然のことながら、映像上でのストーリーの進行は、状況説明や登場人物の内的感情の描写を十全に伴っていないために、どうしても細部に至るまでのフォローは想像力によって補うしかない。だが幸いなことにといっていいのか断言はできないけれど、映画に基づき、青山自身によって小説『ユリイカ』が書かれているので、それを参照し、背景のディテールを詰めてみる。
 (文庫)
(文庫)
小説『ユリイカ』の最初の章は「津波」と題され、山を見つめ、高速度で津波が近づいてくるようだと思っている梢のモノローグから始まっている。映画の冒頭のナレーションとは梢のモノローグでもあったのだ。そして次の章は「一九九二年八月十三日」となり、これがまさにバスジャック事件が起きた日だとわかる。その予兆として、「火山が爆発し、海の向うで戦争が始まる、経済が破綻する」ことが起きたとされる。それらは九一年の雲仙普賢岳の爆発、湾岸戦争の始まり、バブル経済崩壊をさし、そうした大状況において、「世界の端っこの国のその端っこの町のさらに端っこ」にあるカナダ風ログハウスでの生活が対置され、バスジャック事件が起きていく。
その日の沢井の行動を追ってみる。田と隣り合っている家を出た沢井はバスを発車させる。造成地に建てられたログハウスに住む兄妹はバスに乗る。続いてバスジャック犯人、団地居住者のサラリーマンたち、初老の女性などが乗り合わせ、バスは進んでいく。映画では整備された幹線道路として出てくる。次に広い駐車場にバスが止まる。バスジャックされたのだ。小説によれば、第三セクターが造って潰した遊園地の廃墟、「取り壊すにも金がかかり過ぎて放置する以外手の施しようもない夢の残骸のような遊園地の大駐車場」となっている。後に沢井はそこで思うのだった。「俺は憶えている。誰もが忘れたとしても自分だけは忘れない。そしてあの兄妹だけは忘れない場所だ」と。
次にバスジャックのおける犯人、沢井、兄妹の心象を抽出してみる。「自分だけは透明」で、犯人にとってもどこからやってきたのかわからない存在と設定され、後に雲仙普賢岳のボランティアの一員だったのではないかという噂も流れることになる。犯人との意味のわからない会話を通じて、沢井は「このわけのわからん怪物を前にしてどうすればいいのか、この耐え難い緊張から解放されるなら死んでもいい」とさえ願った。直樹も「また死に魅いられた」し、梢も後になって「あの時死ぬべきだった」と思う。生き残った三人はバスジャック事件をくぐり抜けることによって、死に呪縛された存在と化してしまったのである。二年が過ぎ去っても、それを沢井は山を見ていてフラッシュバックさせる。
沢井は呆然と山を見つめた。すべてが同じだと思っていた地面が、夢のように崩れていった。動けなかった。この足元の大地も、決して均一にあるわけではなかった。仕事を始めて以来、ここだけは健康だと、頭に描いた幸福を邪魔されることもなく生きていけると思い続けたことは、そして二度と問うことなく、忘れたままにしておくことができると、そう多寡を括っていたことどもは、すべてが幻に過ぎなかった。いま、何もかもが露になる、と思った。自分の足元の地面が、流れる水のように透けて、その中をバスが横切っていくのが見えるようだった。自分が運転し、異邦の王子の生まれ変わりのようなあの男に拳銃で脅され、奪われ、血に汚れたあのバスが、とうとう動き出した。逃れようはないのだ。そう思った。(後略)
冒頭で梢が山を見て、大津波がくると思ったのも、沢井の心象と同様なのであり、沢井と兄妹が「共棲」し、そして街から「出発」することによってしか、その呪縛を解くことができないのだ。しかもそのために入手した国道沿いの中古車センターにあったマイクロバスは普賢岳の救助活動に使われたものだとされている。ということは前述したようにバスジャック犯人との同行をも意味していることになろう。
沢井の心象の中で、犯人は平家落人部落や古代の古墳の中から出現してきた「異邦の王子の生まれ変わりのようなあの男」「わけのわからん怪物」となり、ただの死のオブセッションの象徴からメタモルフォーゼし始めていた。そのような犯人のイメージの変容のかたわらで、町の外れにできた新しいスーパーマーケットのアミューズメントパークのようなにぎわいと対照的な、新興住宅地になるはずだった雑草だらけの造成地、その一角にある荒れ果てたログハウスの光景などが挿入されている。
それらは歴史から切断されてしまった九〇年代の郊外の風景であるかのようで、犯罪や事件の、ひとつのよってきたるべきところを暗示しているかのようでもある。また映画以上に小説『ユリイカA』は、中上健次の『枯木灘』を始めとする作品群の大いなる影響のもとに成立しているとも思われる。
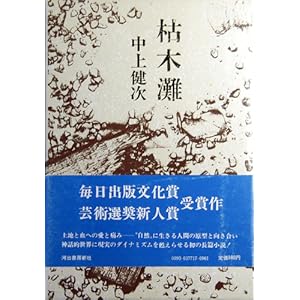
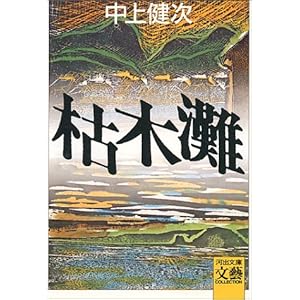
『ユリイカ』は映画であれ、小説であれ、二〇一一年の3・11以後、もう一度観られ、読まれなければならない作品だと断言してもいい。願わくば、拙文をきっかけにして、何人かの観客や読者が生まれますように。
| ◆過去の「混住社会論」の記事 |

