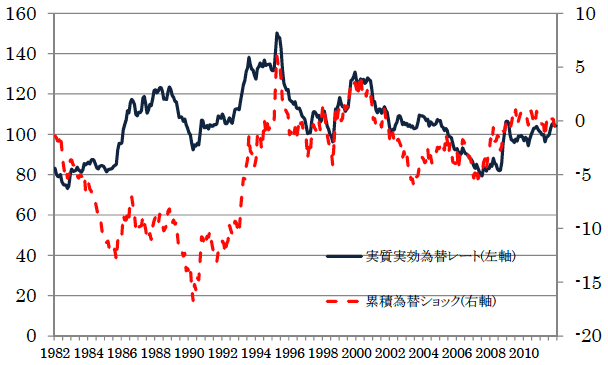| 執筆者 |
祝迫 得夫 (ファカルティフェロー) 中田 勇人 (明星大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 輸出と日本経済:2000年代の経験をどう理解するか? |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「輸出と日本経済:2000年代の経験をどう理解するか?」プロジェクト
日本のマクロ政策論議においては、常に為替レートの変動が輸出の増減を通じて景気に与える影響が重要視されてきた。しかし円レートの変動のかなりの部分は、実際には海外と国内の景況の違いや原油価格の変動にも影響を受けており、為替レートと国内景気という二変数間の関係性のみに注目することは、政策論議の上で間違った結論を導いてしまう可能性をはらんでいる。この問題を定量的に分析するために本論文では構造VARの枠組みを採用し、外生的ショックとして世界景気と原油価格のショックの存在を仮定したモデルの推計を行った。
図1には1980年代以降の実質実効為替レートの動きと、構造VARを使って海外需要と原油価格要因の影響を取り除いた、為替レート変動に固有な「ショック」の累積的な変動がプロットされている。両者の動きはかなり異なっており、たとえば1985年半ばから86年にかけては、プラザ合意に伴う円の実質実効為替レートの大幅な上昇が発生している。しかし外生的なショックの影響を取り除いた為替レート固有のショックの系列を見ると、むしろ1980年代前半の継続的な円安ショックであり、1980年代半ばに発生した円高はその揺り戻しであったといえる。またプラザ合意の前後には、原油価格の大幅な低下が進んでおり、この時期の為替レート変動のかなりの部分はその影響を受けた円高であるため、実質実効為替レートの上昇に比べ、為替レート固有のショックによって説明される円高の大きさは限定的である。むしろ為替レート固有のショックによる円高傾向が顕著なのは、バブル崩壊後の1992年頃から1995年半ばにかけての時期である。一方、2008年秋のリーマン・ショック以降の円高に関しては、プラザ合意の時期と比べても実質実効為替レートの水準の変化はさほど大きくない。
本論文の後半では、他の要因を一定としたときに為替レートの純粋な変動が日本経済に与える影響を分析するために、全産業や規模別・産業別の売上高を、構造VARによって推計された為替レート固有のショックの系列に回帰した式を推計した。その結果、為替レート固有のショックによる円高(円安)は日本経済全般には確かにマイナス(プラス)の影響を与えるが、産業の違いや企業規模によって影響には大きな違いがあることがわかった。一般に輸出競争力があるとされている自動車や電気機器の大企業では、円高は企業の売上高に明確にマイナスの影響を与える。これに対して、非製造業の中小企業ではむしろ円高はプラスの効果を与える傾向にある。つまり(金融政策などによって)円安誘導を行うことは、確かに日本経済全体としては総合的にプラスの効果の方がずっと大きいが、 個々の産業・企業のレベルでは、その影響は大きく異なっていることに注意しなければいけない。